7日、JR東日本はE926形「East-i」の事実上の後継として新型検測車「E927形」を再発し、2029年度にデビューすると発表しました。
この車両は同時に開発を行う次期秋田新幹線車両をベースにするとしており、事実上E6系の後継車も開発中であることが明らかとなっています。
「E927形」のデザインや愛称、また次期秋田新幹線車両の形式名や導入時期はどのようになるのか様々な事に注目されます。

新幹線検測車「E927形」2029年度に導入(次期E6系をベース)
JR東日本は、次期秋田新幹線車両(E6系(こまち)の後継車)をベースとした新幹線専用検測車E927形を2029年度に導入すると発表しました。検測エリアは東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、山形・秋田新幹線で、最高速度は320km/hです。
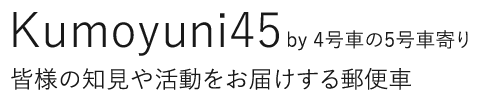


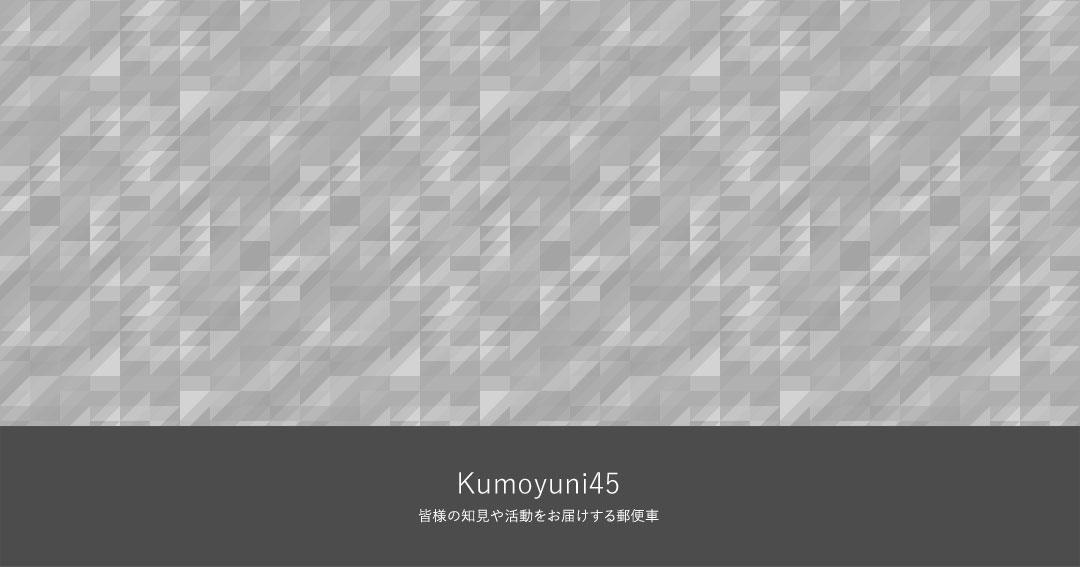
コメント
どちらもE8系ベース…と言いたいところですが、E8系はノーズが短縮されているため、最高速度は300km/hとされています。そのため、足回りはE8系の設計も一部流用しつつ、車体は320km/h運転対応のため、ノーズの延長など、様々な設計変更が行われることになりそうです。新型車両のイメージパースも、ノーズがかなり長めに描かれているように見えますし、ノーズの延長は確実でしょう。
E8系がE6系ベースとの解釈が一般的な様ですよ.
320→300㎞までしか出さないからノーズを短くして,車体傾斜システムを省いたと.
E11系では,よほどの新機軸がない限りは,基本E6系ベースにより近く戻るだけだと思います.
E6系後継車について、先頭形状はE6系並みのロングノーズとなるでしょうが、全席コンセントは確実として、先頭車の乗降ドアはE8系同様、運転台寄りとなり、座席配置はE6と同じになりそうですね。形式名はE11系、デビューはE10系運用開始の約2年後となりそうですが、製造本数は現在と同様、23本か、またはE6系の製造本数と同じく24本かが気になります。
新しい秋田新幹線用の車両E11系?はE10系と電装システム的には同じ,
車体はミニを限界まで攻めたE6からあまり変わらずといったところでしょうか?
時期的には,E3(営業開始1997~),E6(営業開始2013~)と,16年程度で置き換えているので,
2029年度にE11系がでてもおかしくはありませんが,320㎞とE6系と性能があまり変わらない為,
急いで置き換える必要はなく,旅客用登場まで時間をかけるのかもしれません.
新型検測車「E927形」を事実上の試作車として,編成分離等問題が起きないように使い倒すのでしょう.
東海のドクターイエロー廃止などいった最近のトレンドに乗っかって営業用車両に検測機器を搭載するようになるのか?と想っていましたが、
JR東日本の新幹線ではもうしばらく「非営業の検測列車」として残るんですね。
営業/検測兼用としても共通の編成をそのまま使用できる東海道-山陽と違って、JR東日本の新幹線では路線毎に形式がバラけてますからね。
E5・E6・E7・E8と、それぞれで専業路線がある(別形式で代替できない)各形式の一部編成に一式搭載するよりは、検測専用車両を別途製造して全線で運用させた方が低コストなのでしょう。その点もあって、今後も専用車両製造を続けるものと思われます。
唯一、軌道検測装置のみE5・E7の各1編成に積まれていますが、あくまでその専用車両の予備という位置づけのようです。
全線を単一形式で走破している東海道山陽新幹線と違って路線ごとに別形式を走らせている東では営業車計測では搭載編成が増えすぎるという事のようです。
各所に計測編成を配置した在来線とは別の判断になったみたいですね。
>各所に計測編成を配置した在来線とは別の判断になったみたいですね。
いやいや、在来線でも同じ判断ですよ。
JR東日本の新幹線でも軌道検測のみは一部の営業用車両に搭載されていますし、在来線でも同様で、あくまで営業用車両で検測するのは軌道だけ、架線や通信・電力といったそれ以外の検測は新幹線と同様に検測専用車両のEast i-EやEast i-Dを使って行っています。(ちなみに軌道検測についても、JR東日本の新幹線路線では更に精密な測定を行う保線車両がこれらと別に居ます)
実際、JR東日本でも数年前に新型の架線設備モニタリング装置を開発しましたが、その本搭載車両は営業用車両ではなくEast i-Eでした。
結局、在来線こそ営業用車両に地域ごと1編成搭載などでは対応しきれず、かと言って複数編成への搭載や、或いは各路線毎に検測装置一式搭載の編成を配置していては余計に高コストになるわけで・・・
これまで新幹線用検測車はデビュー済みの営業用車両をベースに設計されていましたが、今回は営業用車両が「従」に回ったということはEast-iの代替が喫緊の課題であり、(営業線最高速かつ新在直通である)E6系後継開発のタイミングを待っていたということでしょうか。もしくは、営業列車による検測のみの方針から変わったのかも知れません。
また、これまで秋田新幹線直通列車は東北新幹線の最高速列車と併結でしたが、最高速度が360km/hではなく現行止まりの320km/hということで、札幌延伸後の東北新幹線の運行体系に注目です。
東京駅ホームドア設置というニュースと合わせて考えると、車体長編成長とドア位置は現行E6と揃えてくるのではないかと思います。
随分先の話になりますが、E8の次期型はどうなるかですね。
どちらも基本的にはE8系ベースの開発になると思いますね。最高速度がE8系+20km/hなので、先頭形状はE6系に準じたロングノーズになるでしょう。
E6系後継については、ホームドア対応などもあるので、中間車両はE8系とほぼ同じ車体設計になり、ドア位置も揃えられるのではないでしょうか。
それにしてもE6系も量産先行車の登場からもう15年になるのですね・・・
走行中の分離対策、冬季の単独運転における減速時の滑走対策、夏の高温環境下での機器類熱暴走対策も、新型車の設計には盛り込んでいただきたいものです。