本日JR東日本から、ぐんま車両センターの電気機関車(EF64 1001・1053 & EF65 501)とディーゼル機関車(DD51 842・895)の営業運転終了が公表されました。
後継はGV-E197系で、機関車全廃計画の一環であることは明らかです。
同計画は2018年度時点の秋田総合車両センター掲示から、この時点で2024年度中までに完了することが窺える状況でした。
今年度秋というEL・DLの引退時期は秋田での情報と一致する動きですが、一方で配給列車を中心に未だ機関車の稼働割合が大きいことから、2024年度中の全廃を疑問視する見方もあるようです。
ここ数年は情勢の変化が激しく、鉄道車両計画も大きな影響を受けたと思われますが、JR東日本の機関車全廃計画はどうなっているのか、気になるところです。

ぐんま車両センター所属のELとDLが営業運転終了へ
本日発表されたプレスリリースによりますと、ぐんま車両センターに所属している電気機関車とディーゼル機関車が、老朽化を理由に2024年秋で営業運行を終えることが発表されました。 返信:鉄道コムによると、「客車の前にSL、後ろにGV-E197系1
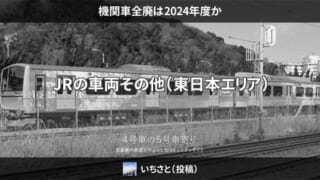
機関車全廃は2024年度か
18日の秋田総合車両センター公開で、機関車の全廃が掲示に明記されており、2021年度から2024年度にかけて行われることが分かりました。検査周期を加味すると2024年度が全廃年度になりそうです。秋田総合車両センター内掲示物よりE257も入場
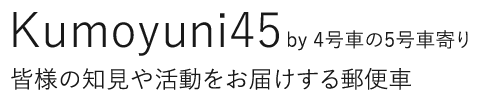



コメント
DD51も引退みたいですが、E655系の非電化区間牽引の後継車はどうなるのでしょうか。
まだGV-E197系による試運転がされておらず、またE655系の編成も相当重いはずなので気になってます。
令和時代に非電化区間でお召列車が走ることなんてありえないので気にしなくて良いのでは?令和の天皇は鉄道嫌いなので。
観光団体列車としての役割は四季島が担ってくれているので、そのへんは問題無しとの判断が利いているように思われます。
やるとすれば、DE10ではないでしょうか?
DD51では?
お召列車やご乗用列車は令和元年には設定されていたが、コロナ禍になってから今まで1度も設定されていないので、コロナ禍やその後の宮内庁や陛下の方針の変更があった様に思われます
平成初期も数年運行されていなかった時期があったので、鉄道に興味がある国賓が来ない限りこのままの可能性がありそうです
E655系に搭載されたエンジンは非電化区間での車内への電源供給用なので、自走は不可能ですね。
既にレール輸送と砕石輸送に関しては置き換え車の本格稼働が始まっていることから、少なくとも双頭式連結器を備えた一部のEF64とEF81以外に関してはいつでも撤退できる準備が整っていると考えてもよさそうです。
ただ、直近の調達予定や統計の動向を見る限り、鎌倉向けのE235系の製造が完了すると予想される来年度初頭以降、最低2〜3年程度は新車がほとんど投入されない時期が続くこととなる可能性が非常に高いことから、双頭式連結器を備えた車両についてもE493系へと置き換えられる以前に単に用途がないことを理由に廃車が進む可能性も十分考えられそうです。
新車の投入がなくても機器更新などの配給列車は走るのでEF64やEF81の廃車はありえないです。
技術が進歩して今度こそ勾配線区で10両を牽引できる牽引電車が登場するまでは残るでしょう。
10両程度の編成をそのまま輸送するならともかく、編成を分割して牽引する方針であればE493系でも対応できる可能性はありますね。
どちらにしても長編成の牽引が出来ないという情報の出所が未だ疑わしいので何とも言えませんが。
確かに、連結訓練までしておいて結局使用されなかったという点は不自然とも考えられますね。
(ちなみに、鶴見線205系の配給はEF81牽引かつ中央線を通らない郡山宛てで行われました。)
そもそもE493系では担えないとする根拠自体が怪しいところではありますが、それを抜きにしても中央線へのグリーン車導入に関連した工事が一区切りとなり、その分東京、大宮、長野の業務量にも余裕ができることを考えると、秋田で首都圏エリアに配置されている車両の工事を行わないことで配給輸送の機会自体を消滅させる(あるいは付属編成等の短編成に留める)方向とすることも難しくないように思えます。
いずれにしても事業用機関車の全廃自体は覆っていませんから、鎌倉向けのE235系を筆頭にコロナ以前から進行している新車や廃車、機器更新計画の遅延分以上の延命はないと考えるのが自然でしょう。
現在JR東日本の在来線車両工場(総合車両センター)が、北から秋田(旧土崎)、郡山、長野、大宮、東京(旧大井)と5カ所あります。発足当初は新津(現在J-TREC)と大船(鎌倉を経て廃止)もありましたが、MF化された車両で検査周期が延伸、さらにTBMの時代となり、車両工場としての業務量が漸減しているだけでなく、今後少子高齢化で車両保有数が減るとなれば、中長期的に更なる縮減もありうることになるかと思います。
うろ覚えですが、確か郡山は車両検修を縮減して部品センターかするという話が一度はあったかと思いますが、盛岡・仙台・郡山・水戸地区の車両を首都圏経由で秋田に持っていくのが得策かと考えると、どうなのでしょう。一方で秋田は、JR東日本で唯一内燃機と液体変速機が検修できるという特異性がありますが、愚見ではむしろこちらが部品センター向きかと。長野はJR東日本の路線としては末端に偏っていて、中央東線が回送ルートとして障害になるものの、自走回送が拡大できればさほど問題にはならないのかな、と思います。東京は首都圏の主力ではあるものの、JR東日本不動産なる会社も立ち上がった今、23区内に車両工場を置いておくのが経営上得策なのか、という問題は俎上に上がらないとも限らない気もします(既に徐々に広町地区の開発は進んでいる)。大宮は新幹線複々線の高架下になっていることもあり、東京ほどは経営上の問題にはなりにくいかと。
ということを踏まえて見ると、E493系とGV-E197形を、今の東の機関車をそっくりカバーするほど製作する必要があるのか、ですね。秋田(地区)の入出場、仙石線の入出場には長期的に必要ですが、J-TREC新津から首都圏へ自走できないか、ということなども考えると、答えは自ずと見えるように思えます。
整理していくと、牽引でないとダメな配給が短編成しか残らない気がします。
新津新製の車両も長野での廃車も、相当数あるなら運転士がハンドル訓練して自走とすればよく、数が少ないものは短編成になります。
仙石線絡みの4Bが最長になるのでは?
長野での廃車にむけての配給/回送については、中央本線の狭小トンネルを通過可能(なパンタを使用しているもののみ自走可)という条件がありますが、今や満たしてないのは209とE217だけですもんね。
E217のほうは終りが見えていますが、房総の209系はいつまで走り続けるのか判然としません。もしかすると209の廃車は、長野で行うとすると牽引配給とされる可能性がありそうですし、自走回送となれば長野以外の場所で解体が施行されるのかもしれませんね。
ぐんま車両センターの機関車の運転が終了しても、田端の方はまだまだ残るのでは?カシオペアの牽引も、ありますので…。
機関車をなくしてGV-E197系にするのは、SL列車・客車列車の質が落ちてしまうので、よくありません。GV-E197系に機関車の後継は務まりません。SL列車・客車列車はやはり機関車が必要です。
鉄道ファンのモラルの低さが度々話題になりますよね。昨日の大宮の事案とか。まずは鉄道ファンの質を改善すべきではないでしょうか。
2024年度中に全廃ということはまだないでしょうが、EF64, 81も決して長くは使わないでしょうね。交直流をまたぐ輸送でも短編成での配給はE493系で問題なくいけるでしょうし、E231系以降の車両は長野へも自走実績あり。
新津からの配給についても、他社向け車両はJR貨物が輸送していますし、自社向け車両については、E493系との協調運転で動力回送ということも可能でしょう。少なくともE235系後の車両についてはそれを前提に製作するのではないでしょうか。
個人的にはぐんま所属の機関車が保存されるのか、あっけなく解体されてしまうのが気になりますね。カシオペアは経年的に考えると機関車全廃とともに引退ではないでしょうか。
郡山総合車両センターについては改造業務からは撤退し、受け持ち車両の定期検査業務のみに集約したのでは?と考えます。山手線への新車投入に始まる転用工事や既存車両の機器更新工事などからは一部を除き郡山では実施されていません。
そもそも論ですが、今回のJR東日本の機関車全廃への動きは、要員面(機関車と電車・気動車では操縦方法が大幅に異なる)と検修面(JR貨物で旧型式機関車の先が見えた今、少数車両の部品調達コストの上昇や、検修ノウハウの維持が困難となることが明白)で不可避なわけです。また、E493系の長編成牽引上越国境越えも、過去の貨物列車の出力重量比を考えれば非現実的という論拠が解りません。
何より、動態保存に最適と思われたぐんま車セから真っ先に用途廃止の情報がオープンになったことを踏まえれば、現有機関車の検査期限を超えた使用継続はまずあり得ない、と考えるのが自然ではないでしょうか。当然、カシオペアの運行終了もここ1,2年のうちに現実となるでしょうし、E655の非電化区間直通も(GV-E197で物理的には可能でも)ほぼ無くなったとみてよいかと思われます。
機関車関係で唯一残る疑問は、非電化区間のお召列車対応です。東日本は主幹会社ですし、自社非電化区間にお召列車を走らせることはない、キハ110があるから良い、とは言えないでしょう。四季島に置き換わっているのでしょうか。
現在主に稼働している機関車として新潟のEF64/EF81が挙げられますが、こちらの機関車の走行距離をできるだけ節約するために、「営業運転を終えた後の」ぐんまの機関車が走行距離の許す限り首都圏内での配給を担う可能性もゼロではないかもしれませんね。
カシオペアの運行予定も7月以降は無く、双頭機など必要最低限以外は無くしてしまうのでは?と感じました。