京成電鉄は中期経営計画で3200形を2025〜2027年度に90両導入すると明らかにしました。これは従来の新車導入ペースより格段に上がっています。なお、2025年度は12両の導入であることが発表されたことから、残りの78両が2026〜2027年度の2年間で導入されることになります。
現在京成電鉄で代替の進んでいる車両は3400形・3500形・3600形及び旧新京成電鉄時代に代替が行われていた松戸線8800形非リニューアル車がありますが、それらは合計して76両(芝鉄3500形3540編成を含む・内装リニューアルのみ行い機器未更新の8800形8815編成は除く)で、今回明らかとなった3200形の製造両数はそれより14両上回っています。
果たして3200形の大量導入により代替される具体的な形式・編成はどうなるのでしょうか?

京成中期経営計画公表(2027年度までに3200形90両導入)
京成電鉄は本日、中期経営計画「D2プラン」を公表しました。既報の新型有料特急導入のほか、2025〜2027年度(D2期間)に3200形を90両導入する計画だと明らかにしました(35ページ)。 返信:中期経営計画で触れられたそのほかの情報につ
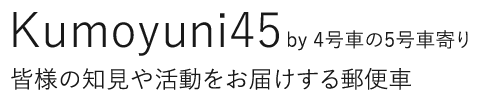


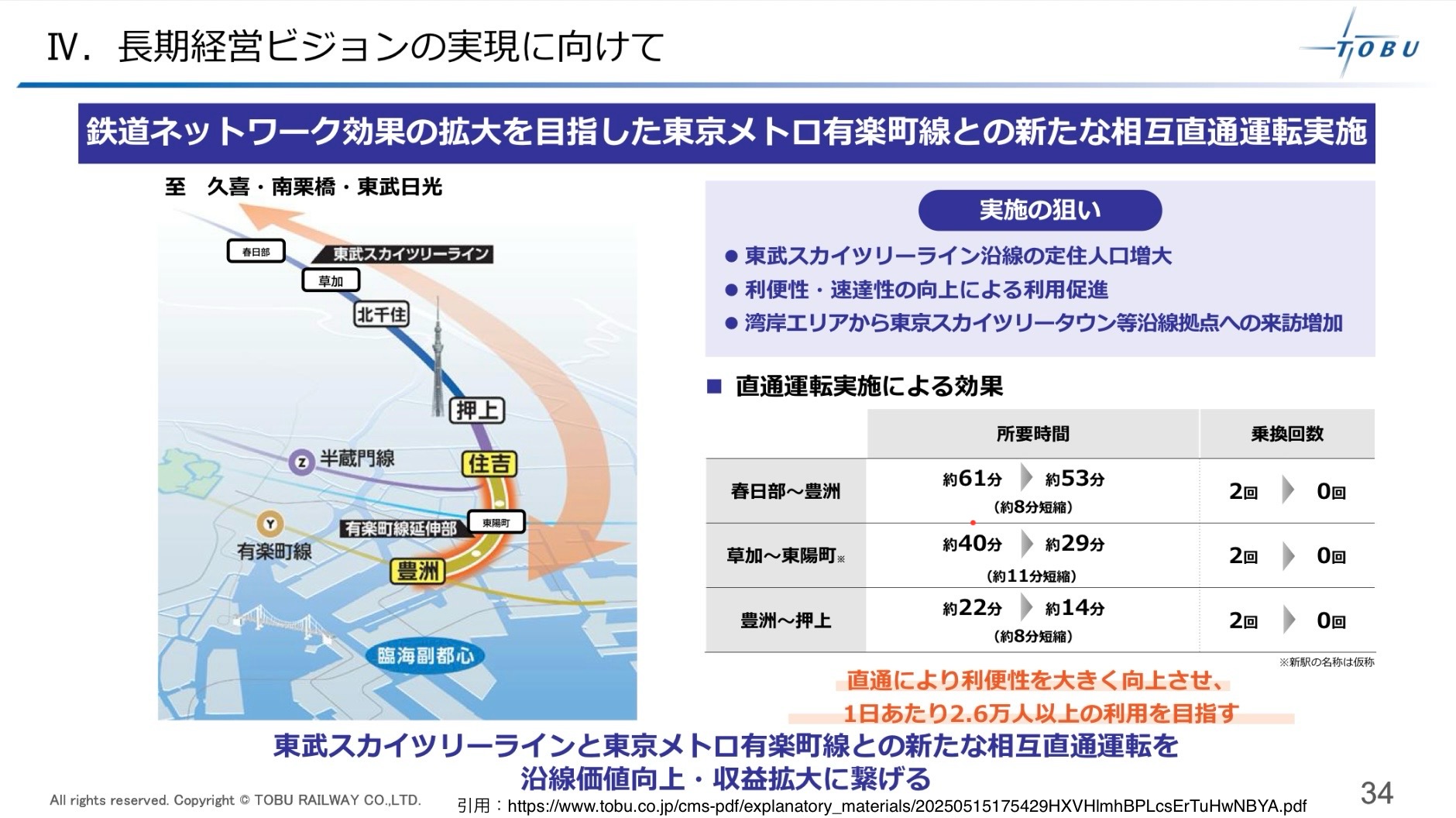

コメント
3400形 8両
3500形 40両
3600形 10両
8800形 直通非対応車 12両
8900形 18両
で計88両
3200形置き換えによる車両運用効率化を考えると80両切るでしょうから8800形の部分的な更新車にも廃車がでるかなと
新型特急車増備後は再び3200増備再開で2030年代前半には8800形も全廃されると思います
更新済みで直通非対応の8806編成ですが、未更新車を差し置いての廃車はあり得ません。直通対応で未更新の3編成の置き換えが優先されると思います。そして、これらの編成のいずれかから直通用機器を移植させればいいだけのことです。
上記の方と同意見で、一番可能性が高いのは8800形機器更新車かと思います。京成唯一の鋼製車ですので優先されそうですが、VVVFのステンレス車より省エネらしいので一考の余地があります。
また、置き換えられそうな車両としては8900形が思い浮かびます。松戸線内でしか運用できず、ワイドドアを採用していてかつ6連3本と少数派だからです。3200形より4両多くはありますが、運用調整で対応できるように思えます。機器更新も14年~16年にかけて行われていて、93年~96年製造ですので、維持コスト的にもちょうどいいのではないでしょうか。
もしくは、8815Fと8900形2本を置き換えたうえで、8900形1本は予備部品が尽きたら廃車という流れも考えられます。
時期的に成田空港輸送強化用の分も入っていたりしそうですね。
最終的に複線化までやるつもりなら当然本線・スカイアクセス線とも一般列車の直通は増やすでしょうし。
3400形の置き換えを3200形で行うのかが微妙なところですね。東武30000系の前例がありますから、4+4で都営線に入れるのは慎重になるべきです。上野方面に運用を限定することも考えられますが、夕方の都営線全振りダイヤでは少し厳しいところもあると思います。4+4を津田沼で切り離し千原ワンマンとセットで効率的に運用するのも面白そうですね。
それこそ3400形については8連用の新形式を設計して、3700形初期車3編成と同時に置き換える可能性もありそうです。
2両単位にできるので、2+4+2にすればそのあたりの問題は分散できると思います。
というか3500形でもこのような組成をしていた時期があったはずです。
3700形は初期車も機器更新車の部品で延命するかなと思います
3700形初期3編成は先頭車に車椅子スペースが無いようですから、(これだけが理由にならないにしても)置き換え優先度は高そうかと思います。
今や乗り入れ界隈の同世代車(都営5300形→既に消滅、京急1500形)でも廃車が出ていて当たり前な時代ですから、3700形初期編成も新型へ真っ先に置き換えられてもおかしくは無いでしょう。
確かに3400形を置き換えると単純にどうしても中間に先頭車が来る3200形は混雑する直通運用で不利ばかりか置き換える車両から8連は多くて1、2本のみしか組成出来ず乗務員訓練等の理由から本線のみに限定されるのは明らかです。よって、置き換えるのには不利な点が多くあります。そして、2,3年以内に置き換えが決まっているはずの3448編成の車内照明LED化は蛍光灯の製造中止2027年以降も車両を使う意思があるという裏付けになると思います。
3448編成は3700形初期車と共に別形式で置き換える可能性が高いですね。
3400はあくまでも予備車でしょう
車内照明LED化は3000形などの更新予備としてあと数年残すためだと考えられます
まずは、3400形(初代AE形)と3500形、3600形を置き換えて、京成保有の車両を全てVVVF化すると思われます。
また、新京成独自の車両であった8800形と8900形のうち、少数派である8900形は先に置き換えられるでしょう。8900形は京成では珍しいボルスタレス台車と三菱製IGBTを使用しており、通常京成保有の車両の多数は東洋電機製のVVVF車です。
また、京成千葉線に乗り入れず運番表示器が使用されなかったり、乗降促進スピーカーも設置されていなかったり、他の車両と違ってワイドドアを採用していたりするなど、現在の京成電鉄にとって扱いにくい車両だと思われます。ですので、8900形は8800形よりも先に本線から退くでしょう。
宗吾の新工場が完成して稼働するまでは非VVVF車は動かすと思われます。一番の理想は運用の一部を他社車両にあげるか、予備2本しかない京成に対して、予備3本もある北総からリース中の3700形を1本返却してもらうかですが。
置き換え対象については車齢や機器更新からの年数に応じて概ね古い順になるものと思われますが、短期間でかなり纏まった数を投入することもあり、単なる老朽車の置き換えだけでなくワンマン運用を行う列車の本数や線区を拡大することも目的として考えられそうでしょうか。
この場合、例えば3000形6連などのワンマン拡大に伴い捻出された車両を松戸線に転用するような流れも発生するかもしれませんね。
京成は最近新造両数と廃車両数が一致する傾向にあるので単純計算だと3600、3500、3400、8800形未リニューアル車を廃車にした後の残りの14両は3700形一本と8900形一本となるでしょう。しかし、旧3200形、3500形が96両でとどまっていることから28年度以降増備再開されるとは限りません。今後本線や千葉線の4両運用を増やし、4両分浮かせて18両の8900形すべて置き換えるのが合理的かと思います。
3700形廃車する理由はないかと
ステンレスで多数派ですから
ステンレス多数派ですが初期3本は経年35年、簡易リニューアル、SIV更新から10年なのでこのままだとそろそろ廃車が出てもおかしく無いです。
今回発表された計96両の3200形で少なくとも3500形46両3600形10両8800形未更新車18両といった老朽車に加え、ドア位置や車体長から松戸線外への乗り入れが困難な8900形18両の92両は置換える事が出来る計算になり、ローカル系統の置換えは一段落つけますね。3400形や3700形といった8両固定車は2028度以降に成田空港の拡張を見据えた投資として新系式を起こしてそちらで対処するのではとおもいます。
3400形と3500形(と3600形?)までの置き換えは確定しているとして、これらが置き換えられた後についてどうなるのかが気になるところです。
普通に解体されるのか、はたまた保存されるのか、あるいは動態の形で残すのか
(さすがに他社転用は無さそうですかね)。
以前のテーマを思い出したので、ご参照ください↓
https://kumoyuni45.net/archives/7695