7月28日に発売予定のイカロス出版『ビジュアルガイド首都圏新系列電車2025-26』の目次に「E501系、JR九州に譲渡へ」と記載されていることが分かり、同系列がJR九州に譲渡されることが事実上判明しました。
JR九州がJR東日本から車両を譲受するのは2008年の415系以来で、奇しくも同じ常磐線・水戸線で活躍していた車両が再び九州へ渡ることになりそうです。
415系は4両編成3本の計12両が、JR東日本で車籍を抹消された後に甲種輸送で九州に向かっていますが、直近の他社譲受である東京臨海高速鉄道りんかい線の70-000形は鉄路を経ない陸送と海上輸送で九州に向かっています。
E501系は運用を離脱した5両編成2本と、運用中の10両編成4本・5両編成1本が在籍していますが、譲渡車両の内訳や輸送方法、改造メニューや九州での用途など、今回の譲渡に関する具体的な車両計画はどうなるのでしょうか。

E501系、JR九州へ譲渡予定
今月28日に発売予定のイカロス出版の書籍の目次にて、「E501系、JR九州に譲渡へ」との項目が確認できました。東京臨海高速鉄道りんかい線70-000形に続き(参考)、同形式もJR九州に譲渡されるようです。関門トンネルなどに投入され、旧国鉄の

Re:415系12両、JR九州へ
今日は有休(元々取る計画でした)をとって、水戸駅まで行ってきました。編成組成は12/17に私が申し上げた通りで、機関車はEF81-84による牽引でした。>水戸線民様、Rascal様はじめまして。フォローありがとうございます。K525,

新門司港で東臨70-000形とみられる車両が確認
30日、福岡県の新門司港にてブルーシートに包まれた東京臨海高速鉄道70-000形とみられる車両が確認されています。70-000形を巡ってはZ8編成の両先頭車がブルーシートに包まれた状態で東京港まで陸送されたことが確認されており、東京港から新

70-000形2両が小倉総合車両センターへ搬入
新門司港で目撃されていた70-000形2両ですが、本日未明、JR九州の小倉総合車両センターへ搬入されました。フレンドに誘われるままにりんかい線70-000形の追っかけしてました。小倉工場に入ったようですが、これからどうなるか楽しみですねぇ
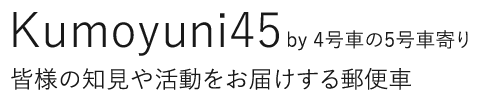



コメント
415系の老朽取替用として使用するのは間違いなさそうですが、全てを置き換えるには編成数が大幅に不足しているので、E501系固定編成で福岡エリアの2,3編成併結運用を置き換え→解放した複数編成で415系を置き換え、などといったことをしない限りは、巷の大方の推測通り交直流電車を要する関門トンネルを通過する運用分だけ置き換えるのでしょうね。
現状関門通過運用は5運用程度のようなので、大幅な見直しがなければ、最終的にはSAKIGAKE以外の全てのE501系を譲り受け、5運用1予備の体制にすると思います。
https://ameblo.jp/qr-tsubame/entry-12845232100.html#Fo
編成が組めれば甲種で持っていったほうが確実に楽だし、輸送費も安いです。
りんかい70-000形は、先頭車だけだったから編成が組めず、バッテリーもありません。甲種回送時にブレーキ作動させられないから、海上輸送せざるを得なかったものと考えられます。
たとえ電源が無くとも、車両メーカーからの甲種輸送のようにブレーキ装置を仮設すれば線路上の輸送は可能です。
それでも海上輸送が行われたのは、Tc車だけをJR線上に出す手間(八潮に機関車を入線させるか、JRの車両基地まで回送し編成組み替え)や、1編成ずつしか廃車にできない事からこの手間を複数回繰り返さないといけない事が原因かと思われます。
E501系はある程度まとめての輸送になると思われるので、かつての415系のように甲種輸送が行われるのではないでしょうか。
E501系4扉車が,関門トンネル用に転用するのは予想外です。
長崎地区で導入されているハイブリッド気動車が415系を置き換えると思っていました。
YC1のことですね
九州大学鉄道研究同好会が作成した運用表をベースに行きますと、415系1500番台は12運用あり、そのうち関門トンネルを通る運用が5つ、残り九州完結運用が7つとなっています。一方E501系は10両4本、5両3本あり、観光用の5両1本除いても6本と、関門運用は賄えるので、現存するE501系全車譲渡することはできると思います。
ただし、E501系は50Hzのみですので、60Hzへの改造や10両の短編成化はもちろんのこと、今の415系は関門と九州完結両方できる前提の運用を組んでいるため、E501系が入る前までには運用の見直しは行われると思います。
60Hz化に伴う機器交換と4両編成への短縮ほか最低限の改造にとどめ、「即戦力」として関門運用を中心に使うと思います。
輸送方法は、今度は編成で輸送すると思われるので甲種輸送を使うでしょう。
415系の置き換えは521系の九州仕様かなぁと予想していましたがまさかの展開です。
関門運用以外は交流車で賄えるので、運用分離して関門運用をE501系、九州完結運用は821系かそれ以降の新系列での置き換えでしょうね。
小倉~下関間は約15分、現ダイヤで1時間当たり2~4本の運転となるとダイヤを調節すればラッシュでも3運用で回す事も可能になります。そうなるとE501系の転出規模はどうなるか、考え物です。
・10連のみ転出、6or8連に短縮して使用
・10連と5連両方転出、10連は6or8連、5連は4連化して使用
・10連と5連両方転出、全編成4連化して使用
関門区間(小倉〜下関の機織り)+送り込み程度であれば5運用程度で賄えることからも、付属編成2本に加えて基本編成4本の計6本が譲渡されると考えるのが妥当なところでしょうか。
ただ、運用に関しては引き続き鹿児島本線で415系の運用が残る(残さざるを得ない)ほか、既に日豊本線では西小倉と安部山公園の一部ホームに固定柵が設置されていることからドア数の異なる車両の運用が困難である点を考えると、415系とは異なり南福岡に配置される可能性が高いものと思われます。
ただ、調べてみたところ鹿児島本線でもホーム柵ある駅がいくつかありますね。
現在の415系は荒尾・佐賀までの運用がありますが、快速停車駅の大野城がその中に含まれているので、柵を撤去しない限り南福岡までの乗り入れになりそうです。
素人です。
試運転の記事見て…もしかしたら?と思っていました。
どうせなら、全部あげて…「運用次第でお好きにどうぞ」的な風になるのでは?
ただ…先頭車が不足…
まさか、りんかい線の先頭車と組ませる?わけないか。
最悪、幕張の209置換えの際に「ちょうだい」されるかもしれません。
確かに先頭車だけ209系も譲渡と言うのは有り得そうですね
モーター無し車の交直流化改造に幾ら掛かるのかは不明ですが
りんかい線の車両が先頭車だけ九州に来たのはE501のサハと組ませるため?
E501を編成単位で貰うと、サハは確実に不要(10両編成ならモハも余る)
りんかい線のクハ(トイレ設置)+E501サハ+りんかい線のクハ(電装化してクモハ)の3両で103を置き換えるとか?
それならりんかい線のサハを貰った方がいい気もしますが、E501を編成単位で貰う話が先になって、りんかい線の話が後から決まったとすれば?
りんかい線のクハの電装化の段階で「模型か近江鉄道」レベルの組み合わせだと思うので、
まだ我々が想定していない展開があり得そうです。
小倉車両センターの匠の手にかかれば(劇的改造ビフォーアフターの鉄道版)
輸送方法ですが他人様のXなのでリンクは避けますが
「鉄道 5両以下 陸送 安い x」でググると
新潟トランシスの方が「5両以下なら陸送の方が安い」だそうですね
まあ時代や場所、距離によって変動はあると思いますが
今回は5両なので陸送かもしれません
が、距離が距離なのと5+5で10両なら甲種で輸送した方が安いみたいです
甲種鉄道車両輸送を貸切列車で行う場合、運賃計算トン数が最低で400tというのが約款上のルールです(輸送準備にかかる手間賃を収受するためと考えられる)。となると、短編成ではどうしてもコスト的には不利です。E501の10連基本編成でも編成重量が400tには満たないかと思いますが、割安感は大幅に上がるかと。
415系の残存車の置き換えはYC1系のようなハイブリッド気動車だと予想していました。
気動車ならば、下関から日田彦山線への直通も可能になるだろう、と思っていましたが、常磐線のE501系譲渡になるとは思っていませんでした。
新潟トランシスの例は最寄りの貨物駅まで陸送しなければならない制約によるものです。
ここまできたら東臨の先頭車と組ませてしまえ~、って本当になりそう笑
興味深いのは、VVVFやSIVといった主要機器が60Hz対応しているか。案外床下機器を作る重電メーカーは、わざわざ周波数を分けずに両対応で製造している可能性もあるかもしれませんね。
これまで出回っている匂わせ情報(過去に趣味誌連載などもされていた方ほか複数より)などから、どうやら9月上旬に2本まとめて郡山~小倉で甲種のようですね。
E501系は、水戸線内では投稿時現在完全ワンマン化していてそれに対応した機器を積んでいないからというのもありますが、具体的な事は言えませんが交直切り替え機器に不具合がある様で水戸線内が完全ワンマン化する前から運用に就いていません(入線したとしても下館以東の交流区間のみ)。
このことから交直切り替えのある関門トンネルの運用につくのではなく、現在運用しているのと同様に交流線区限定で走らせるのだと思われます。
自動切り替えに不具合があるだけで手動での交直切替は特に問題ない可能性もあるからなんとも言えない所ですね
自分も水戸支社社員の方から交直切り替え不具合で水戸線外れた話は聞きましたが、先週、乗務員訓練で水戸線走っていたというのもあり60hz対応の時に何かしら対策とかの目処が立っているのかもしれませんね
50Hz専用車を60Hz対応改造させるのは不可能と言うことではないのですね(新製とかデンチャとかイカ釣り漁船(YC1)とか521とかいろいろ考えてE501にしたのですね)
関門間の需要や415の編成を考えると、以下のようになるのでしょうか。
A いくつかの駅にある、3ドア用のホーーム柵の存在から関門間の置き換えにほぼ特化し、それ以外の運用は別途用意する交流専用車両で置き換え
B E501は4両とし、サハ(10両身体とモハユニットの一部)は東日本にて廃車解体か九州に来ても部品取り(運用にはつかない)
C ワンマン化は微妙(関門トンネルのワンマン化は実施するのか?)
Aについては、回送にするか快速で通過にする手もありますが、西小倉は快速停車駅なので微妙ですね
(821の6両版を追加で作り、813-600を置き換えて813-600は元の3両に戻し415の単独運用を置き換え?※821の増備再開も検討はしている模様)
Bについては、5両以上は持て余しそうですし…まさか筑肥線同様、先頭車の電装化で3両以下にする⁉そこまではさすがにしないかと思いますが、あり得ないとは言い切れない気もしてきました
50Hz車を60Hz対応にするには、交流特高圧機器(トランスやリアクトルかな?)の積み替え乃至改造でしょうね。
形式名はどうなるのでしょうね
K501系とかに変わるんでしょうか
小規模な改修のみで運用するならEを外して501系、現在入場している70-000形のように別物のような車両に生まれ変わるなら違う形式(400番台の空き番号や503以降)になると予想します。
話題を見て、りんかい線からの先頭車と合わせて、4連を大量に用意して(片方の先頭車のみE501系とすれば強引ですがトイレ設置も不要?)415系を一気に置き換えるのか?と妄想してしまいましたが、ホーム柵があるとのことですと、考えにくいでしょうか。
ところで元りんかい線車両の転用先はJRから明言されているのでしょうか?
可能性は否定できませんね……
明らかになっているのはりんかい線からの譲渡は先頭車のみ10両という点だけです。
当初先頭車の輸送が確認、直流4ドアという関係から103系が残る筑肥線への導入が濃厚と判断され、先頭車のみなのは改造内容が多いからや、中間電動車は他の編成から持ってくるのではと予想されていました。
その後先頭車のみの譲渡が明らかとなり、電動車化改造をするのか?と見られていましたが、E501系の10連からモハユニットを組み込むとなると、4連10本を組むことが出来ます。その場合、E501系10連は両先頭車がトイレ付なので、1~3号車と7・8・10号車で分けてりんかい線の先頭車と組めば、見た目は若干……ですが少なくともトイレ設置という大改造は避ける事が出来ますし。この場合りんかい線の先頭車の使用は8両ですが、残りの2両は部品取りと考えればおかしくはありません。
一方、鹿児島本線や日豊本線の一部の駅で3ドア位置での柵があるようなので、関門運用と筑肥線で車両共用でしょうか。
直流専用にすれば周波数対応不要ですね りんかい線にしても501にしても両数はっきりしないしどっちも4連で筑肥線だったりして
一部駅設置の3ドア位置のホーム柵ですが、車両側に締切スイッチを付けて当該駅では車端部の2ドアのみで客扱いを行い、ドア位置の合わない中央2ドアは締切扱いを取れないものなのでしょうか
3ドアのホーム柵は415などに対応しているので、E501とかりんかい線の4ドア車の車端ドア位置とは異なるため、柵の一部交換や間口拡大などしないと物理的に難しそうですね
今から投入ならワンマン化もするでしょうし、中編成ワンマンで開閉ドア数を一部駅だけ変えるのはトラブルのもとになりそうなのでやらないかと思います
気動車だと距離のあるトンネルは向いてないので、交直流電車のほうが良いということなのかなと思いました。
今イカロス出版の当該書籍の目次を見たら「E501系、JR九州に譲渡か」に変わってましたね…
内容が確認出来ないので分かりませんがもしかしたらイカロス出版担当者の妄想記事かもしれません
さすがに甲種予定など把握した上での記事かと思いますし、そうでは無ければ出版社の信用問題になると思います。
少なくとも単なる妄想で章を起こした商業誌は前例がありません。
配置については距離的には最も近い直方というのもあながちないとは言えなさそうなようですね。
713系の置き換えや今後の3両以上でのワンマン拡大を考えたとき、送り込みや間合い運用により817系や821系を若干数でも捻出できる余地を持たせられるのはメリットとして小さくはないような印象があります。
あくまで非公式である出版社の書籍の見出し文を鵜呑みにのすのは早計かと思います。
仮に関門運用に就くにしても、交直切替装置の老朽化に伴い切替不全が多発した結果、急遽デッドセクション通過運用を禁止された曰く付きの車両です。
JR九州からすれば関門区間の為だけに交直対応の新形式を興すのは腰が引けるので、方針を見極めるまで他所からの譲渡車で凌ぐという選択肢は有りだとは思いますが、肝心の切替部分に不安のある車両をわざわざ導入するでしょうか?
仮に譲渡が決定したともなれば、内装は勿論電装周りから大規模修繕は必須となり、その内容は西武鉄道のサステナ車や筑肥線向けに譲渡された70-000系の比ではない大掛かりな物となるでしょう。
塗装変更と内装の小改造、保安装置の交換以外はほぼそのままの西武8000系と、走行機器を0から設置しなければならない70-000形を同列に並べた意図は分かりかねますが、不安があるなら修繕すれば良いと判断したのでしょう。元々設置されていたものですから、新設よりは改造規模を小さく出来ます。
もちろん譲渡についての信憑性は本の発売を待たなくてはいけませんが。
交直切替ですが、水戸線と違ってほぼ門司駅構内、徐行しながら通過するようなので、「手動切替で十分」と判断したのではないでしょうか。JR九州も素人ではないはずですから…
十分というよりも、そもそも自動切り替え自体はATS-Pの機能を使用したものですから、ATS-Pに類する保安装置の導入されていない九州では使用できません。
50Hzの変圧器は60Hzで使えるので改造は不要みたいですね。
効率が良くなると変圧器メーカーは言ってます。
国鉄車両も50Hzを基準に設計してたみたいですし。
此方のサイトですね。エビデンスありです
https://fa-faq.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/13044
E501系はVVVFもSIVも主変換器から出力した直流を使用していますが、交流→直流の変換器は50Hz対応品を60Hzで使用する事ができません。
降圧する主変圧器は、仰る通り周波数が変わっても使用は可能と思われますので、最低でも主変換器は改修ないし交換が必要です。
E501系が現在走る常磐線ですが、水戸線っていがっぺ?様の運用調査の表に寄ればE501系とE531系の10両の運用を足しても3+21=24運用でE531系の10両が26本と輸送力はともかく置き換え自体に支障はなさそうです。
https://mitoline.web.fc2.com/database/unyou/index.html
415系の時と同様、高萩等の疎開先から九州へ譲渡されるのか郡山総合車両センター等に入場して譲渡されるのかが気になるところです。
その場合、置き換えに回るのは基本編成ではなく付属編成単独あるいは2併結になるので、10両の編成数に関してはあまり意味がないところです。もっとも、5両に関しては0番台・3000番台合わせて40編成に38運用なので正直なところ余裕は全くありませんが。
すなわち、それこそがこれまでE501系10連を置き換えられていない理由なのでしょう。
黒磯-新白河間といわき-原ノ町間からE531系が撤退。そのかわりに幹カタに新車を投入して、ステップなし701を台車交換のうえ転用とか。元々どちらも昼間は701系2両がワンマン運転していた区間ですし。配線略図.netさんのサイトによると、黒磯駅構内の配線と架線が整理されたそうなので、上り本線デッドセクションを那須塩原方の1〜3番線からの合流手前、下り本線は高久方4〜5番線の合流手前に移設して、4番5番ホームを交流に戻すんじゃないのかなという。みたいな。
なるほど、黒磯駅構内をなぜ直流化したか全く理解していないわけですね。
そうやって構内に並行して別の饋電系統を混在させていたことが原因で過去に死者を出してますし、ここを通るのはなにも普通列車だけではないのですよ?それら列車の取り扱いをより複雑にするのは運行上何もメリットがありません。
さらに言えば、その区間はどこも客車ホーム採用区間で、701系5000番台やE531系のような電車ホーム対応車両である必然性すら本来ありません。交直流車両に客車ホーム対応形式が存在しないがためにE531系を使っているだけです。ここや他のデッドセクションにおける運行系統を考えるとそのような形式が出てくることは今後も無いでしょう。また、この区間は福島県手前、新白河のふたつ隣の豊原まで、常磐線は宮城県手前の新地までが首都圏本部(それぞれ旧大宮支社、旧水戸支社)の管轄であり、そちら側所属の車両であるE531系で運行するのはごく自然なことです。
基本編成での置き換えについてですが、過去に朝方の高萩始終着列車でE531系基本編成とE501系10連の運用持ち替えがしばしば行われていた時期もあり、単純にG車の営業区間をいわき(草野)まで伸ばして基本編成で置き換え、とするのは合理性はある印象は受けます。
元地元民ですが、やはり人口減・少子化の潮流もあり、(白電置き換え当時はともかく)輸送力の面でも今実質8連で問題となる運用・区間はそこまでないかなぁとは。
あくまで余剰車活用=上野口の基本編成所要はもう増えない、というのが全ての前提にはなりますが。
ただまあ九州譲渡前提で東日本側が車両計画を立てるわけではない(出物を作りに行くことはない)わけで、九州側としては出物が出たので確保しておいた、というレベルに留まるような印象は受けます。
関門間置き換えは、「デンチャ」BEC819系またはYC1系にすると思っていました。最近のJR九州は、単一系列化による数の理論で導入コストとメンテコストを下げる傾向にあると感じてましたので。
10両編成については先頭車化改造で2編成に分割する可能性もあります。
こうなるとSAKIGAKEと廃車分を除いて10編成となり、関門の他に福岡都市圏の分も賄えますね。
>10両編成については先頭車化改造で2編成に分割する
10両編成ってほぼ全車川重の2シート車体ですがそんなこと出来るんですか?
車端部で強度を得ている車体を切断したら車体強度が著しく低下しますが・・・
強気なコメントですが、従来工法の東急・新津・大船製と違って訓練機械レベルを含めても完全に実例がないとはいえ、「2シート工法車は先頭車化『できない』」と証明されたことは一度もないのでは?
209系以降の先頭車化の件はやはり風説の力が強いようで…
まあそれはそれとして、3ドア前提の設備が導入されている部分もある以上、E501系に広範囲の活躍を見込んでそこまでやるとは思いませんけど
>車端部で強度を得ている車体を切断したら車体強度が著しく低下しますが・・・
在来工法に比べ車端部を切断すると、2シート工法のみ車体強度が著しく低下するソースをお示しになると根拠になるかと思います。
209などの初期新系列車は
・10年しか車体強度が持たない
・先頭化や電装化など出来るはずがない
・上記の事から譲渡など行われるはずがない
と今までさんざん言われてきましたが、結果はご存じのとおりです。
これらはすべて、在来車に比べ強度が低「そう」という根拠やソースのないデマからの憶測・妄想だったからです。
こちらの管理人がコメントしていますが、13年で車体寿命を全うする(≒車体強度を在来車と比べ大幅に下げつつ運用可能にする)車体設計は技術的に不可能です。
https://4gousya.net/jr_e/4462.php
起こった事実に目を向けると普通の車両と変わりません。201系は大規模改造、譲渡いずれも行われていませんが、「だから車体強度に問題があるに違いない」などという人はいませんよね?
なので強度が落ちる技術的なソースがあれば万人に納得が得やすいと思います。
また、個人的には譲渡されたE501の先頭車改造はしないと思います。経年車にそのような高コストな改造せずとも交直流が必要な関門運用は回り、交流専用車なら821やその後の車両を新製すればよく、する必要が薄いと考えられるからです。
まず2シート工法の設計からして、「側柱を省略して外板のみで車体強度を得る」つまり構造的には車体全体で強度を確保するというモノコックの設計思想と同じです。
たとえばアルミニウム合金車体の先頭車化改造が難しいのは加工性もそうですが、特に近年のダブルスキン車体のような完全にモノコック構造の車両では車体の切断など設計に無い開構造を造ってしまうと強度が確保できなくなるためです(そこが強度的に脆弱になり、元々の剛性の低さも相まって歪みが生じやすくなる)。
これと全く同じ理由で、2シート工法で妻面にビードを用いているのは車体強度確保のためと公式に書かれており、すなわちモノコックだけでは強度を確保しきれていない、あるいはシートの歪みの発生を妻面で抑えているとなれば、これを切断したらどうなるかは明らかではありませんか?妻面以外に車体全周を支える構造体が無いわけですから。
在来工法では全周を支える骨格がありますから、切断しても新たな構体をそれと接合することで強度が確保できますが、骨格が省かれているこれら車体構造ではそうもいきません。381系の先頭車化も、当時はアルミ車体でも骨組み構造だったために出来たことなのでしょう。
ところで、209系0番台やE501系では車体全長について先頭車が中間車より長い構造になっています。実際のところ、製造元に関わらず209系の先頭車化改造が避けられたのは、この車体及び台枠の延長が現実的ではないからだったのではないでしょうか。
209系では側扉間隔が現在のガイドライン準拠(4820mm)の車両より長い4940mmであるために、中間車では1番または4番客用ドア-直近車端部間の線路方向空間が1.7mもありません(ガイドライン準拠や旧来寸法では約1.85-1.9m)。209系の乗務員室全長は約1.85m、E721系以降の3ドア車体においても約1.95mありますから、これでは乗務員室の空間を確保できません。205系の先頭車化では前面強化やE231系に準じた運転台形状、また伝送系増加などによるスペース確保のために車体を200mmほど伸ばしているそうですが、それでは済まないほどの構体延長になります。
どうやらこの寸法はE231系以降、最新のE235系においても変わりないようなので、今後も転配のたびに同じ問題が付きまといます。コロナ禍後の保全体系の抜本的変更にも、その要素が少なからず関わっているのではないでしょうか。
唯一先頭車化改造によって登場した訓練車は中間車の構体ほぼそのままだそうですが、それもあくまで車籍の無い訓練車だから、と。実際乗務員室は本来の先頭車と比べてかなり狭いようです。統合モニタはなく、MONといった伝送系が搭載されているかも不明瞭です。
以上、長文失礼いたしました。
車体強度はともかく、209系以降の東形式の中間車車体はドアと車端までの距離が短く車体延長するかドアを中間よりに移設しないと新設する運転台スペースが取れないですね。
>これを切断したらどうなるかは明らかではありませんか?妻面以外に車体全周を支える構造体が無いわけですから。
妻面を切断したままならその可能性はあるかもしれませんね。しかし先頭車改造では新製先頭車と同様、代わりに先頭車の部品を付けます。なのでご指摘の前提は崩れるかと思います。
新製先頭車含め車体は、側面と妻面or先頭部分を接合して製作しています。解体画像からも明白なように先頭車も中間車同等の2シート構造で、です。
213系改造車のような、車端部数mを切除する事を想定されておられるようですが、東日本が改造した205系は妻面部を取り外し先頭部分を付けています。209系訓練機材も同様です。
すなわち、新製では先頭部分+側面+妻面を接合して制作してる物を、妻面+側面+妻面の片側の妻面部分を取り外し先頭部分に付け替えることになります。構造的に同様になります。
ここで、強度に関係しそうな乗務員扉の開口の疑問が出ますが、中間車のその部分は、もともと乗務員扉より幅の広い窓と窓を開けるための空洞部分であり構造的に似通っています。
同じような工法と部品を用いて改造すれば、同じような強度が保たれる事は想像に難くないのではないでしょうか。この事からE501含め「2シート構造だから先頭車改造は困難」とは言えないと考えます。
>209系の先頭車化改造が避けられたのは、この車体及び台枠の延長が現実的ではないからだったのではないでしょうか。
209系を先頭車化改造する必要がありません。無改造で房総地区のすべての在来車の置き換えを完了しています。房総地区向けの改造期間から考えれば、先頭車改造し他地区も置換える事のほうが現実性が乏しいように思います。
再度になりますが、201系が先頭車改造がなされなかったのは、201系が「先頭車改造できない」からではありません。する「必要がない」からです。201系なら誰でもすぐ納得する事です。
新系列や2シート構造車の先頭車改造事例が無い件についての多くの考察は「先頭車改造できないに違いない」という考察者の結論に基づいて理由を探しているような印象を受けます。
>実際乗務員室は本来の先頭車と比べてかなり狭いようです
訓練機材は新造先頭車と比べ10数ミリ程度寸法が違うそうですが、ご指摘の乗務員室の広さの違いは、訓練用の分厚い壁を用いた特異な開放構造がその主な原因かと思われます。
209系の新製先頭車を見ればわかる通り乗務員室仕切りとドア間にはE233系等のトイレ部に比べまだ余裕があり、先頭車化による寸法の違いは十分吸収可能です。
長々と失礼しました。
>すなわち、新製では先頭部分+側面+妻面を接合して制作してる物を、妻面+側面+妻面の片側の妻面部分を取り外し先頭部分に付け替えることになります。構造的に同様になります。
>ここで、強度に関係しそうな乗務員扉の開口の疑問が出ますが、中間車のその部分は、もともと乗務員扉より幅の広い窓と窓を開けるための空洞部分であり構造的に似通っています。
>同じような工法と部品を用いて改造すれば、同じような強度が保たれる事は想像に難くないのではないでしょうか。
それがまさに骨組みがある従来工法の場合の話ですね。切断しても単体で自立し、新旧構体の骨組み同士を溶接することで旧来の強度を維持しています。乗務員室扉のために開口部を広げたといっても、外板が車体を支えているわけではないので関係ありません。あってドア周辺を環状に補強し骨組みと接合・溶接して終わりです。
しかし、骨組みが省略されている2シート工法(モノコック)では妻面切って構造開けたら最後です。外した所から歪みが生じ始め、そこに新たに妻構体を接合しても元の強度には戻りません。そこが構造上弱点であり続けます。全体で強度を得ることによる副作用で、自動車における事故車と同じです。
そのためにアルミダブルスキンの話を先に持ち出したのですが、ご理解いただけなかったようで。
>209系を先頭車化改造する必要がありません。無改造で房総地区のすべての在来車の置き換えを完了しています。房総地区向けの改造期間から考えれば、先頭車改造し他地区も置換える事のほうが現実性が乏しいように思います。
>201系が先頭車改造がなされなかったのは、201系が「先頭車改造できない」からではありません。する「必要がない」からです。201系なら誰でもすぐ納得する事です。
>新系列や2シート構造車の先頭車改造事例が無い件についての多くの考察は「先頭車改造できないに違いない」という考察者の結論に基づいて理由を探しているような印象を受けます。
そうですか。確かに支線区の置換えは205系で果たしていましたから必要は無かったでしょうし、先頭車化改造しようにも205系以前と違いMM’ユニットが全然ありませんでしたからやる意味がなかったのは間違いないですね。それにしても、その定義や201系の話にこだわるのは何か願望でも入っていらっしゃるのですか?
私個人としては、新系列車両に求められる乗務員室空間を考慮すると、先頭車改造できないというのが間違いとは思いません。
単純に前例がないから、「不可能と考えられている」、
その不可能な理由をあれやこれやと推測しているに過ぎないと思います。
実例が出てくれば、その推測は間違っていたことになりますし、
実例が出てこなかった場合は、その推測が正しかったかもしれないし、
単にその必要性がなかったからの可能性もあります。
ここや他の場所で言われている“根拠”は、これらの推測を裏付けるには十分ですが、
真実かどうかは誰にも分かりません。
「不可能ではない」ことを証明するのは困難です。
「できないと考えられているが、もしかしたらできるかもしれない」
これ以上の答えはないかと思います。
散々強気の「できない」論を展開していたのに、結局
>私個人としては、新系列車両に求められる乗務員室空間を考慮すると、先頭車改造できないというのが間違いとは思いません。
という個人の感想になったのが残念でした。
209系以降のマイナスイメージの根深さは深刻であると同時に、「する必要がない」「やっていない」を「できない」と勝手に変換してしまう趣味者の持病も垣間見える討議でした。
確かなことは、下記で説明されている「大菅踏切事故対策」がなされていない運転台は、JR東日本の前頭運転台としては使用出来ないということです。
ttp://www.jreu.or.jp/static_page/03safety/page04.html
113系など当時存在した車両はいわゆる「鉄仮面」など、簡易な対策に終わりましたが、それ以降に新造・改造された先頭車は、ひとつの例外もなく大菅踏切事故対策を実装していることもたしかなことです。
新系列の中間車を先頭車改造するには構体に手を入れる必要がある、故に極めて高コストになるというのも、技術的なことなので、ほぼ確かなことでしょう。
誤解が生じ方なところとして、これはあくまでも「JR東日本の独自対策」なので、他社の場合は一切関係ないということです。
(前頭運転台の強度基準は、法律などでは特に定められていないはずです)
まあ、輸送の仕方は東臨の運び方から考えると多分船だと
水戸の車は531系が入ると考えて他に501の10両もモハ1組とサハ4両は解体して九州に入れることはSAKIGAKE以外はなさそう。
自分は10両そのまま入れるのはないと考えます。
E501系をJR九州に譲渡するのであれば、415系を置き換えると思われます。ただし、E501系の空いた分を常磐線では補わないとならないので、さらなるE531系の増備が必要となりそうですね。どうなるかはわかりませんが。
来年増備ですか?
くだんのムックが発売されましたが、文面としてはあくまで推測調で書いているようですね。
ただ、目次が公開された当時、おそらく内部情報も知っているだろうなという方の複数名が、「やっと公開になった」や「情報解禁された」といった表現で呟いているのを見ていますので、まあそういうことなんだろうなと思っています。
E501系の基本編成10両4本を4両編成8本に短縮する際の先頭車には房総209系で余剰になったクハを使用するかもしれません。
伊豆急譲渡から外れたクハを使用する可能性があります。
直流クハを交直流クハに改造した例にはクハ455の一部やクハ401-101がありますね。
>房総209系で余剰になったクハを使用するかもしれません
209系とE501系は見た目が同じなだけで実際には車体から全く別物ですが、そのあたりは問題なさそうですか?
クハに追加でいろいろ積むことになりますけど。
ちなみに前回の伊豆急譲渡の際には6連を譲渡したので先頭車は余りませんでした。
「TWR70-000を2連で使う」という話が公式に出ていない(推測情報しかない)と仮置きした上ですが、あの先頭車10両のうち8両を501の基本4編成分の先頭車として使い(2両は事故対応や部品取りのための予備)、どちらも少数派となる筑肥末端用と関門用の編成を共通化してしまう(予備削減)、といった妄想をしてみます。