11日にJ-TREC新津から出場した仙石線用E131系800番台。
従来のE131系ではVVVFインバータは日立製のものが使用されていましたが、今回出場した800番台は外見が異なるものとなっています。
果たして、今回仙石線用E131系800番台で採用されたVVVFインバータのメーカーや詳細はどのようなものなのか、また従来の車両から変更された理由が気になるところです。

仙石線向けE131系800番台が新津出場
本日、仙石線向けE131系800番台センN1編成が総合車両製作所新津事業所を出場しています。これが仙石線の新車かぁ。J-TREC(新津)からE131系800番台センN1編成がついに出場!・・マジ貫通扉ない。 pic.twitter.com/
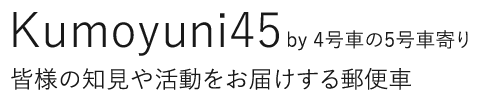



コメント
関係者でないのと資料の発見と読み込みが出来ていないので、詳述しようにも出来ませんが、三菱製(の最新のもの?)ではないでしょうか。メーカーに関してはそのような目撃が既にあったと思います。
全く同じものというのはないと思いますが、設計が水平展開されていて、納入時期の近いと思われる他鉄道事業者、例えば東武80000系(電動車が1M構成)や未登場の同社2連ワンマン新車と酷似した機器だったりしたら面白いですね。
E235系の製造が一段落し、三菱との関係を維持するために参入させたのではと思います。
コロナが無ければE233系が仙石線に導入予定だったことから、当初は想定してなかった導入分として新しく設計した結果、このようなマイナーチェンジ気味な仕様に決まったのかなと思います。
半導体不足の影響がここに出たのではと推測します。
三菱では足りなかった分、日立からも受注してたのではと思われ、半導体の需給が回復した今では三菱から安定して納入できるので三菱を採用したんじゃないんでしょうか。
半導体不足がなければ、E235系と並行して造っていた71-000やE131系500,600,1000などは皆三菱VVVFだったと思います(最終的には納入先がどのメーカーのものを取るかにはなってしまいますが)。
それぞれの調達時期を考えると、少なくとも600番代あたりまではコロナ以前の発注となりますから、半導体不足は全くもって関係ありません。
E131系の場合、モニタ装置も日立のSynaptraベースのシステムが採用されるなど、全体的に日立製の装置の採用が目立っていることから、当初はE235系等の首都圏向け長編成に三菱電機製の装置を、地方向け短編成や特急型に日立製の装置を採用する方向で一定の棲み分けを図ろうとしていたものと考えられます。
しかし、コロナ禍の影響により三菱電機製の機器を採用するはずだった首都圏向け長編成の新規投入が当面見送られることとなったことから、発注先のバランスを取るために当初計画になかった地方向け短編成(800番代以降のE131系)においては三菱電機製の装置を採用することとなったと考えるのが最も自然に思われます。
なお、E131系800番代についてはVVVF装置以外にもブレーキ制御器が従来のナブテスコ製から三菱電機製と思われるものへと変更されていることが確認されていることから、その他にも採用メーカーの変更が生じている箇所が見られそうです。
調達先の分散は経営の基本。既存形式の機器更新分も含めて、日立と三菱の両方に発注することでリスク分散とコスト削減を図っていますね。
仙石線E131系にはATACSが必要であり、日立製MONやVVVFと協働できるATACSの拡張システムを仙石線向け車両だけに新規に開発するより、同所で製造されていて同じくATACSを装備する東臨71-000と近い三菱製パッケージを採用した方が利点があったのだろうと思います。
利点はコストとスピードでしょうか。