2018年11月、田園都市線から大井町線へ転用された東急2000系2003Fが営業運転を開始しました。
しかし翌12月には、長津田に入場していた元2000系2002Fが9020系9022Fに改番され、さらに2019年2月には、すでに大井町線で運用されていた2003Fも再び長津田に入場し、編成組み換えを経て9020系9023Fに改番されました。
2003Fとして大井町線で運用されていた時期は、暫定的な編成であった事が特筆され、結果として「大井町線における2000系」は極めて短期間の存在にとどまりました。
このような一連の経緯の背景には、どのような事情があったのでしょうか。

東急2003F 大井町線で運用開始
東急2000系の2003Fが5両編成となり、本日から大井町線で営業運転を開始しました。大井町方から クハ2003-デハ2303-デハ2453-デハ2403-クハ2103 の5両編成を組んでいます。主電動機交換を始めとした機器の更新のほか、座

2002Fは9020系へ改番
長津田で改造中の東急2000系2002Fですが、9020系への改番が確認されました。元々、運転室内の「9020」表記から9020系への改番の可能性が指摘されていましたが、2002Fから変更されることになります。2003Fも正規の組成になる際

東急2000系2003F、恩田に再入場 ほか
東急2000系2003Fが恩田に再入場したようです。長津田工場では先日廃回された8640Fの脇に到着。デハ8540は前照灯の球が抜かれてますね… pic.twitter.com/LySFzIt7f2— はせゆか。 (@hase_yuka)

東急2000系2003F、9020系に改番
東急2000系2003Fが9020系に改番されたようです。2003F→9023F 改番確認元2302も同様 pic.twitter.com/Z8fdYhlcRW— 國の?道 (@kuni_train) February 7, 2019もと2

東急2000系の「9020系改番」は本当に「2020系重複回避」だけが理由なのか?
現在東急大井町線で運用され、サステナ車両として西武鉄道への譲渡も見込まれる東急電鉄9020系。元は「2000系」という系列番号で、転用時や正規編成に組み換えた際に改番された経緯があります。改番に至った理由として、「M2車(デハ2250,23...
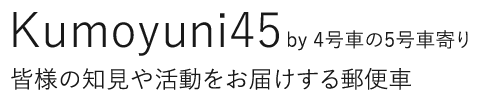




コメント
3編成存在した田園都市線の2000系について、2003Fだけは大井町線に転属する前から更新済みだった記憶があります(とは言っても更新後は試運転のみで田園都市線の運用には復帰せず、そのまま大井町線転用改造を受けたと思います)。
他の2編成は未更新のまま田園都市線を離脱し、大井町線転用と同時に9020系化の改造を受けていたと思います。
掲題にも記載されている通り大井町線2003Fの編成組成はあくまでも暫定的な形であり、なおかつ2003Fから更新済みの2ユニットを他の編成に組み込む計画だったようです(計画通り?)
先に更新済みの2003Fが、将来的に東急が想定する9020系とは異なる組成であるため「とりあえず」2003Fのままで大井町線に投入したのかと思います。
8500系をいち早く淘汰したかった、残りの2000系→9020系が改造している中寝かせるのも勿体ないので足慣らしで先行運用した、の2点が考えられます。
現に2003編成の投入で8639編成が離脱しています。
(本題とは離れますが、大井町線2003編成として再デビューし、9023編成に改番されるまでのあの時の鮮烈な記憶は一生の思い出です。正味1か月半程度の儚い夢のようなひと時でした)
2003Fの奇妙な動きは,おそらく,同時期の他の更新対象の8500,8590の中古販売の都合で,
2000系は田園都市線でしばらく使う可能性も,大井町線へ転属して使う可能性も,
どちらもありうる状況で,どちらにも対応できるようにしたのだと思います.
富山地鉄から結果的には引き合いがあった8694F,8695Fは,
田園都市線で10両で運用していましたが,
軽量ステンレスカーで特に商品価値が高いので,
すぐに売れなければ,最大数年程度はかつての8691~93Fのように
5連化して大井町線で使いづづけるシナリオもあったのだと思います.
この影響で,2000系×3本は,田園都市線での数年間の継続利用と,
将来の大井町線への転属のどちらにも対応する必要があったのでしょう.
対策として,大井町線に転属する場合に使うであろう,
車歴が若い2003Fのサハ以外の8両を機器更新して,
田園都市線で誘導障害等対策を兼ねた試運転を行えば,
田園都市線でそのまま使いづるけることもできますし,
将来大井町線に転属するとしても,重複する大部分の試運転も兼ねられます.
ここで,仮に田園都市線で2000系×3本を使い続けるのなら,
2003Fの機器更新で発生するVVVF等の基盤等の発生品は,
2001~2Fで使うことができ,3本は安定的に田園都市線で使い続けられます.
ただ,現実には順調に8590等の売却が進み,
2000系×3本は穴埋めで大井町線に転属することになったので,
2003Fを組み替えて5連にして大井町線での暫定運用を行い,
大井町線での誘導試験はもちろん営業運転での問題点の洗い出しを行いながら,
田園都市線の2001~2Fを置き換えられる2020系列の新車が出そろうのを待ってから,
2001~2Fを田園都市線から離脱させて,必要な車両のみ機器更新を行い,
新たに2001~3F×5連に組みなおして,大井町線への転属となったものと推察されます.
真ん中あたりは十分あり得る話ですが、頭とお尻は完全にこじつけではないですか?
8590系も界磁チョッパ制御+直流電動機で8500系同様置換え対象ですから、既に9000系転用で撤退した大井町線に再度転属させてまで残す理由は東急には全くありません。それどころか、車両としては突き出すことになる大井町線の8500系のほうが新しいくらいです。ちなみにこの8500系も軽量ステンレスですよ。
仮に富山地鉄への譲渡がなかったなら、同時期廃車の8500系同様そのまま廃車解体して終わりだったでしょう。
東急テクノシステムがある東急の場合,7700系,8000系,1000系,9000系の頃から,
改造の上での譲渡に事業としても力を入れており,
引き合いがある車両なら,無理のない常識の範囲内において
廃車の順序を遅らせる等の対応は考えられます.
また,2003Fが機器更新されて10連で田園都市線で試運転だけされた
2018年頃の車両動向を見る必要があります.
8590扱いの両端先頭車10両は88~89年製で若干若く,
デザインも洗練されていて商品価値は高いです.
8500の計量車体の譲渡対象になりそうな8631~8637Fは83~86年製となり,
若干古く,デザインも古いです.
商品としてみた場合,デザインは無視できない要素です.
※8638~8641Fは5+5用の編成でやや特殊で譲渡に適さず
大井町線から早期離脱させたい意向が働いた可能性があること,
8642Fは先頭は問題ないにしても中間車にVVVFが2種類入る等
試験編成的要素が強いことを考慮して,検討対象から除かれた可能性は高いです.
商品価値の高い8590の廃車を先送りするとした場合,
当時の情勢からは田園都市線での継続利用と,大井町線での継続利用が考えられます.
田園都市線の場合,大井町線よりも重要線区ですから,
サークルKの8606F,8594~95F,2001~03Fは早期に離脱させたいところですが,
8606Fは2020年度まで残っており,8590も+2年の2020年頃残す選択肢もあったと思います.
また,車歴を考慮した場合でも,1975~76年製造の古い8616,17,19Fが
2022年度まで残っているので,中間車が1985年製造の8090である8694~95Fは,
サークルKを除く機器的にはこれ以降まで残っても問題ないことになります.
大井町線の場合,田園都市線よりは重要度が落ちますが,
8638~41Fが2018~19年度まで残っているので,
これらの置き換え用として,2000系ではなく,8594~95を組み替えて入れて,
数年程度しのぐ手もあったと思います.
このあたりは経営判断で無理なくどうにでもなる範疇だと思います.
計画は一通りで済むわけもなく,ある程度冗長性を持たせることも考慮するので,
数年程度廃車を遅らせることはできるでしょうし,
2018年度から本格的に入り始めた2020系の生産を後ろ倒しにすることも,
財務等経営的には合理的な選択になるのでありえたのだと思います.
結果8590は富山地鉄に売れたので,次の置き換え対象の2000系は
大井町線転用ということになったのでしょうが,
2003Fの奇妙な動きは,車両売却の都合で多少の変更にも対応できるように,
田園都市線での10連でのしばらくの利用と,大井町線での5両×3の利用
どちらにも対応できるようにするために上述のような形になったと推察されます.
他に2003Fの奇妙な動きを説明するものも見つかりません.
ちなみに,私個人的には,伊豆急の8000系や,長野の8500系初期車を
田都の8500系の後期車を中心に使って置き換えれば,
車歴を10~15年程度若返らせられるので,置き換える選択肢もあるのでは
とは思っていましたが,これは選択されませんでしたね.
部品単位での流用はできるでしょうし,
甲種輸送までして入れ替える必要まではないとの事だったのでしょうか?
まず、鉄道車両を廃車したら地方へ譲渡しなければならないという考えを捨てましょう。
他社へ譲渡するために廃車とするわけではありませんし、商品価値なるものは貴方の語る妄想でしかなく、8590系を無理矢理残存させる理由には全くなり得ません。
富山地鉄の車両更新と東急の廃車のタイミングがたまたま合った、それだけのことです。仮に前者がなければそのまま搬出・廃車解体して終わりです。
また、東急テクノシステムの本業は電気設備工事やバス車両の整備であり、譲渡改造は(同業の京王重機整備においても)ごくまれにしか来ない小さな副業でしかありません。力を入れる以前の問題です。
デザインが良いか悪いかって個人個人によって判断が分かれますから、
(客観的に考えて)他社へ譲渡する理由にはならないのでは?と思います。
車両を他社へ譲渡する際の決め手としては、
・需要と供給のタイミング
・車両性能や規格など
・譲渡へのコスト
まぁこのあたりが強く関係してくると思います。
あとは、譲渡したい車両の廃車を先送りするという点もいまいち引っ掛かります。
むしろ逆では?
譲渡が決まった車両こそ早い段階で離脱させて改造などに着手すると思いますが。
大井町線より田園都市線が重要路線というのも、何が根拠でしょうか。
東急からすればどの路線だって平等に重要な路線だと思います。
元投稿で「販売の都合」と書いたために、読み手によって理解がずれている、議論が噛み合っていない気がします。
富山地鉄から購入希望は来ているけれども、社外の事情で時期が決め難い、というケースは容易に想像出来ると思います。
補助金の予算年度や銀行借入、業績と設備投資額の兼ね合いなどですね。
東急本体の売却益は微々たるものでしょうが、子会社のテクノシステムの利益を考慮したら、ある程度融通を効かせることは、ビジネスとしてあり得る話だと思います。
> この影響で,2000系×3本は,田園都市線での数年間の継続利用と,
> 将来の大井町線への転属のどちらにも対応する必要があったのでしょう.
2000系については,2003Fの恩田入場前に10連1編成が長津田→逗子間甲種輸送を計画(商業誌にも計画掲載)されながら輸送中止になったり,さらにその時点で,最終的に9020系として残ることになった15両だけが室内灯LED化を施工されていたりもしましたので,現在の形態となるかなり前から,転用構想はあったのではないかと思われます。
身も蓋もないですが、議題で触れている通りで、機器更新したので・5連に短縮しましたので即座に9020系に改めました、ではなく
2002FのM1車を単独Mとして改造竣工させ、正規5連を組める段階で改番しています。
車両管理システムへの新車両番号の設定登録作業を1度にまとめたといったような実務上の手順があったのかなと。
ところで答え合わせはあるでしょうか?
答えとしては、「当初の大井町線2003Fが暫定編成だった」ということになると思います。
2000系→9020系化への流れについて、まず2003Fが最初に改造を受けて大井町線に転用されました。
2001F及び2002Fの転用改造が完了するまでは先に改造済みの2003Fで暫定編成を組んで大井町線に転用するものの、完成形である9020系とは組成が異なることと区別する目的があって2000系のままにしていたと思います。
東急の様な多角的に事業を行う巨大企業においての地方事業者等への中古車販売は,
単純に車両の売買価格以上に莫大なメリットがある美味しい事業なのです.
実際に東急が日比谷線等の1000系も5年もかけて丁寧に売り切っている前例もあります.
理由は簡単で,東急不動産,東急建設,生活サービス事業等
他部門への波及効果が見込めるからです.
地方鉄道事業者へは補助金が政府や自治体から入っており,
真の顧客は都道府県等自治体や国交省,政府で,
弱小の地方事業者ではないことに注意が必要です.
中古車販売で恩を売っておけば,再開発のタワマン等の都市開発や公共事業等で,
東急不動産や東急建設等への受注可能性が増しますし,
百貨店やスーパー,ケーブルテレビや電力等の生活サービス事業の進出,
ホテル等リゾートの進出等へも有利に働きます.
また,東急の中古車が各地で数十年程度走り続ける宣伝効果も見逃せません.
事業の倫理的には赤字にならないか,若干の黒字くらいになればよいですし,
このようなビジネスはB to Bではいくらでもあります.
可能であれば赤字受注をすれば,合法的に事実上の接待等リベート効果を出せます.
東急にとっては,鉄道事業は営業利益ベースで30%程度の重みしかありません.
52%程度を不動産事業,
12%程度を生活サービス事業,
6%程度をホテルリゾート事業
で稼ぎますから,中古車販売はエビで鯛を釣るようなものなのです.
東急車両の売却後に新車販売という意味はなくなりましたが,
その後に1000系を5年もかけて自社用地等に保管しながら売り切っています.
むしろ最近は地方の鉄道事業が独立採算では成り立たなくなりつつあり,
政府や都道府県や市町村等の自治体からの補助が増えつつあるので,
事業としての重要性が増しつつあります.
このあたり,中古車をいくらで売ったか程度の,表面上の認識では読み誤ります.
似たような事業としては,鈴与のFDAによる航空ビジネスがあります.
航空路線を就航させることのバーターで,国や地方での知名度が増し,
物流や,ガソリンスタンド等のビジネス,警備やビルメンテナンス等
他部門で回収すればよいので,航空事業はたとえ若干の赤字程度でも成り立つのです.
逆に,JR東海等は関連事業が大きくはないし波及効果も限られるからか,
211系は三岐鉄道,独立採算の流鉄にすぐ引き取らせて,改造なども請け負っていません.
他方で,JR東日本は独立採算でも富士急の国会議員等も出すほど強い
堀内家に対して恩を売るためか,205系は長野で改造してまで売っています.