5/16、東京臨海高速鉄道りんかい線70-000形Z8編成の車両銘板が撤去が確認され、その後一部車両の搬出も行われています。
一方で、70-000形を巡っては他事業者への譲渡を含めたリユースの検討をすると報じられていますが、Z8編成の現時点で残っている車両の処遇はどうなるのでしょうか?

りんかい線Z8編成が廃車
東京臨海高速鉄道70-000形Z8編成の車両銘板の撤去が確認されました。同編成は廃車されたようです。同編成は今月9日を最後に運用の目撃がありませんでした。妻面の社名入り銘板なくなってて本当に東臨の車両じゃなくなっちゃったんだなぁって感じ…?
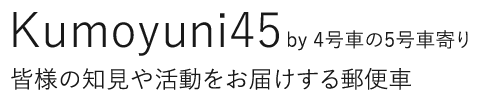



コメント
銘板撤去確認されたのは昨晩搬出された2両のみで、残る8両はまだ本線回送の可能性が残ります。
解体のための搬出が中間車から始まっていることもあり、4年ほど前から公然と語られている某所への譲渡などいろいろと選択肢の考えられそうな状況でしょうか。
ただ、その”某所”へと譲渡されるとしても、そちらの所要数が5編成程度であることから8編成全てが譲渡対象となるわけではない都合、Z8編成がその対象外の中に含まれている可能性も考えられますから、まだ判断は難しそうなところですね。
りんかい線70-000形は10両×8本の在籍でした。
一方先頭車はTcとなっているため、3両以下で組成する場合先頭車化改造が必須となります(訓練車を除き同構造の209系は改造実績なし)。
20m車、4両以上で走行可能な路線はかなり限られると思います。
よくよく考えると3両編成(というか4両以下)を組むにあたって中間車に運転台を設置するのも一つのアイデアですが、元々の先頭車を電装化するアイデアも考えられるかと思いました
(※技術的に出来るか出来ないかはまた別問題です)。
ただし209系列の先頭車に電装化を行った事例は営業用・事業用問わずまだ無かったと思われますので、
今のところは最短が4両編成という認識になりそうなのは変わらないでしょう。
>元々の先頭車を電装化する
技術的に可能かどうかと訊かれればもちろん「可能」です。
それでも実際の譲渡車に制御付随車の電装改造車両がほぼ無いのは、それより中間電動車の先頭車化改造のほうが、改造難易度が大幅に低いということなのでしょう。205系の時でもクハ→クモハ(デハ)に改造された車両は1両もありません。
もっとも、それも理由としてあるでしょうが、209系でそういった改造が無かった最大の理由は、京浜東北線209系の転配が動いていた時期がちょうど205系改造車の地方転用が終わったタイミングで、既に3両以下の短編成を転用投入する必要が無くなっていた、つまり先頭車化改造してまで転用すべき路線がなかったということなのでしょう。となると必然と先頭車を電装改造してまで転用するような路線もなかったわけです。
近年ですとその事例は01系譲渡車や、日比谷線絡みで発生したメトロ03系譲渡車(ここまで2形式はアルミ車体で先頭車化がほぼ出来ませんでしたから已む無しです)や東急1000系1500番台くらいでしょうか。こちらも譲渡車には1両もありません。なお東武20000系に関しては転用車はユニット再利用、譲渡車は全て中間車からの先頭車化改造なので存在しません。
伊豆急、三岐、西武のようにJRと繋がっている会社間での譲渡は鉄路での輸送がほとんどなので、陸送された車両の譲渡はなく解体の可能性が高そうです。
今後譲渡の可能性が全くないとは言えませんが、機器構成上4両が最短編成となるため譲渡先は限られてきそうです。
長野や秩父そして九州と何となくの転用先候補はありそうですが、(全く予想外なところも含めて)他社への転用が本当に実現するのかを注目していきたいですね。
まず209系列の中間車について、本線走行を前提とした先頭化改造の実績がまだ無いことが気がかりな点でしょう。
訓練機械の先頭化改造における強度は、本線走行をしないと分かっているのでそこまで強度を持たせていないという意見を以前別のテーマにて拝見しました。
これが本当なら興味深いものだと思います。
本線走行向けに強度を持たせれば先頭化改造が可能なのか、やはり構造的に強度を増すことが不可能なのか。
この点がはっきりすれば転用の選択肢は広がるでしょう。
しかし8000系が3両編成(単位)で運行されている伊豆急に209系が4両編成で転用されたことを考慮すると、
やはり209系列を本線走行向けに4両以下で組成するのは不可能な気もします。
可能なら伊豆急へも3両編成化して転用していたのではと思いますし、これが答えなのかもしれません。
新系列では新造先頭車は強度向上のパーツがついています。逆に中間車では、従来の中間車より強度を落としています。ですが、209系以降の中間車を先頭車化改造出来ないのは、JR東日本の内規によるものです。
1990年代に、大菅踏切事故という、過積載ダンプに113系前頭運転台が衝突する事故があり、運転士が殉職したため労組が問題視し、その再発防止策として同様の事故でも運転士の命を守る水準の強度として他社よりかなり厳しくなりました。
運転台を付けるだけなら、訓練車で明らかなように、改造は可能です。あくまで事業者の裁量なので、全線踏切が無いとか、ローカルで60km/hぐらいしか出さないとか、条件が異なったりすれば運転台を追設する改造は技術的にも強度的にも従来通り可能です。
>60km/hぐらいしか出さない
伊豆急(伊東線)では明らかに60km/h以上出すような区間があったと思いますから、安全性を考慮して3両化を見送ったのでしょうかね。
何気にかっ飛ばすんですよね。あの路線は。
しかし同じステンレスの8000系は中間車の先頭化も実施しているので何か微妙な違いがあるのでしょうか。
それこそ事業者側の裁量なのでしょうけども。
SNS上などで既に指摘されているようですが、70-000形に採用されている川重2シート工法では側構が側板とプレス加工された骨組のみで構成され、縦方向に貫く側柱を持たない構造となっています。つまり、先頭車化改造といった後から構体へ大規模な改造を施工すること自体、JR東日本の内規の問題ではなく構体設計に起因して不可能であるはずです。もちろん設計段階でそれを考慮したものとなっていれば話は別ですが、70-000形がそのような設計になっているとは聞いたことがありませんので。
>新系列では新造先頭車は強度向上のパーツがついています。逆に中間車では、従来の中間車より強度を落としています。
当時の鉄道趣味誌の資料では「大菅踏切事故を受け従来車両に比べ先頭車の強度を上げた」といった記載は多数ありますが、強度向上のパーツがついているとか従来の中間車より強度を落としているといった記載は無かったように記憶しています。
東急製の例で恐縮ですが、以前209系3000番台の車体構造が露出した状態になった解体途中の画像がネットにいくつか上がっていましたが、先頭車の構造も中間車の構造も驚くほど同じです。
余談ですが、大菅踏切事故を受け在来車の113系列や103系列に付けられた「強度向上のパーツ」は主に先頭車に上付けされた「同じ形のステンレス板(無塗装時は鉄仮面と呼ばれていました)」程度のものだったと記憶してます。
縦方向に貫く側柱を持たない構造だと、後から構体へ大規模な改造を施工することが不可能になる理由がよく分からないのですが…。
新車制作時も別々の部品である側面と妻面を接合して組み立ててると思いますが、その妻面を外し運転台取り付けに適した開口の妻面を新たに接合する訳で、特に縦方向に貫く側柱を持たない構造が問題になるような事は無いように思います。
先頭車改造の場合、おそらく乗務員扉が車端の窓だった位置に付くと思いますが、これも70-000はもともと窓開口のため下部まで空洞構造になっている訳で、その開口部に新製先頭車と同様乗務員扉を接合すれば普通に考えて構造的にかなり似た強度になるように思うのですが…。切断するプレス位置が中途半端ならその部分を切除し新製はするのかもしれませんが。
さらに言えば、205系先頭車改造車の運転室部分の柱のように、最終的に必要であれば後から不足分を補う補強を入れればよい訳で、改造時の設計によって克服可能な問題と感じます。全てはそれが許容できるコストかだけでしょう。
また、SNS上では未だに「寿命半分」を製造後10年程度で廃車必須の車体強度や特殊な工法の車両(≒改造には不適)と誤認してる方もおられ、SNSに書いてあっても正しい情報とは限らないです。
新系列の強度についてはこちらの管理人も記載しています。
https://4gousya.net/jr_e/4462.php
解体を前提とした廃車を行うのであれば長総なり郡山なりに配給輸送するはずですので、東総で銘板撤去を実施したり、陸送搬出しているのが謎ですね(東総でも事故車や余剰車の解体は行っていますが、編成まるごとの場合、その編成中の一部車両の転用計画があっても一旦長野に送るのがこれまでの前例でした)。
今回の陸送については東総ではなく自社の八潮車両基地からの搬出となっており、また搬出に際して車内外の部品撤去が確認されていることから、少なくともこの2両については解体のための搬出と思われます。
JRの車両ではないので、車両基地から陸送の形でもそこまで不思議ではないと思います。
あと廃車に関する作業は東総(東京総合車両センターのことでしょうか?)ではなく、八潮車両基地内で行われたようです。
むしろ長野や郡山に配給する場合は機関車などで牽引の形になるでしょうから、そちらの方が手間ではないかと思います。
まぁ川越車両センターあたりに一旦疎開させてから、機関車で牽引するなんてあり得そうだとは一瞬思いました。
リンZ8編成は全車解体されるでしょう。
リンZ8なる個性的表現のソースはあるのでしょうか
教えてくださいませ
同様の予測をされている方を見かけないのですが、私はJRの房総地区への譲渡の可能性があると考えています。
事実上同型車による置き換えになりますが、70-000の方が製造年が新しく、8両貫通編成を組成することができます。
それによって捻出された209系4両×2本(×8組?)を伊豆急に転出させることが可能ではないかと思っています。
房総地区への転用は、トイレが無くなるからまずあり得ないといえます。
房総地区へはE131系の追加投入及びE233系の転属(転用)により209系を置き換えるようです(計画変更がなければこのままでしょう)。
製造年が新しいと言っても209系との差はほんの数年程度ですので、転用のコスパ的に厳しいかと思われます。
トイレ設置などの改造も出来ないことはないでしょうけど、どうせ同様の改造を行うならE233系の方が更に経年が浅いですからね。
youtubeに東上線のボロを始末するために10両全部譲渡される東武はその前からメトナナメトハチを狙っていたが断念したとデマを書いた者がいます。
最有力の西武が流れた以上九州もデマだと思います。
西武が狙っていたが流れてしまった、というのも一部の方の願望混じりなのではと思っています
70-000形の各編成中間車2両が使われないのであれば、そのKW-151台車16両分に改造を加えてどこかの鉄道事業者向けとして(狭軌以外→)狭軌履き替え用として活用されることはあるでしょうか? いやないでしょうね。
今回廃車陸送車が出たZ8編成は、17年後半に機器更新された3番目に走行機器が新しい編成です。編成自体も02年製造と新しいもののため、公開情報から分かる範囲では譲渡編成にするのに支障があるものではありませんでした。
にも関わらず廃車したということは、9番目に新しいモハユニットと車体が譲渡に不要であると判断されたということになります。
一方、先頭車は3組目に新しいものですから、一定規模以上の譲渡がある場合には絶対に必要になります。譲渡案件が存在するのであれば最低でもどちらかの先頭車は保管される筈です(恐らく譲渡案件自体はあり、両方とも譲渡に備えて保管になると憶測しています)。
残り2組のモハユニットが廃車されるかどうかは、7本目、8本目の譲渡が存在するか(Z1、Z2編成の先頭車を譲渡するか)にかかっていますが、Z1、Z2編成の先頭車は95、96年製造と古いため譲渡されない可能性が高いと憶測しています。このまま機器を取り外された後に搬出されるのではないでしょうか。
但し、現状で話題に上がる秩父鉄道、長野電鉄、JR九州(筑肥線103系の後継)全てが3両編成の運用のため、譲渡する場合には3両化が行われる可能性が高く、その改造は八潮車両基地で行えるものではありません。
譲渡編成の場合も改造場所への移動が行われる筈ですが、それも陸送搬出になりそうです。
Z8編成の2~3号車も搬出されたそうです。(これは事実)
新しく状態の良いモハユニット5ユニット分(つまり、Z8のモハユニットは使わなくて足りる)と、先頭車5ペアあれば唐津の103の置き換えはできます。
(Z8は先頭車だけ譲渡?)
4両化だと輸送力余剰という声もありますが、3両化するコストや電力などのコストが、103系3両と70-000系4両で比べて大差ないか、後者の方が低いとなれば4両化でもするでしょう。
もちろんこれも可能性の1つに過ぎないですが。
過去に何人かが何カ所かで書いてますが、筑肥東線103系置き換えが3両である必要はありません。
元々103系6両固定だけだったのを、半数程度輸送力適正化で3両ずつにしただけです。
当時は筑前前原で分割併合(唐津寄り3両だけが唐津方面へ直通)という運用もあったのです。
しかし10年前にその運用もなくなり、305による置き換え完了後は残った103は前原と唐津を行き来するだけです。
6両固定(実際はクハモハモハ+モハモハクハの2編成併結)は全て305に置き換え済みです。
今の103の置き換えに必要なのはトイレ付車両です。
2両でも4両でもいいのです。
りんかい線の車両を貰うなら、クハモハモハクハの4両でトイレ付ければいいのです。
(地下鉄に入らないので前面の非常口もいらない)
前原のホームドアに対応しているかは重要ですが、深江で系統分断すればこれも解決してしまいそうです。
筑肥線譲渡が有力だと思います。20m級4ドア車しか走らない筑肥線が有力だとおもいます。
別に103-1500の置き換えで3両である必要はなく東臨70-000の最低組成両数4両でもokかと。
筑前前原のホームドアに4両対応プログラムに書き換えすればいいかな〜とおもいます。
トイレは普通に1号車につければいいと思います。
JR九州は821を10本で製造中止するくらいなので新車より使える中古車を望んでます。
丁度置き換えられる東臨70-000を九州仕様に改造すれば20m級4ドア直流中古車が欲しいJR九州の考えに合致します。
しかも数日前に新門司港経由でKKにZ8編成の両先頭車が来た情報がはいってるので正直筑肥線譲渡だと思います。
長文失礼致しました。
このコメントの投稿者です。付け加えですが、別に4両確定ってわけじゃないです。
実際に西唐津〜筑前前原間の運用で6連でもダイジョウブカナ~って思います。
実際に4連の電車がここ最近筑肥線電化区間で使用された記憶がないので逆に6両に統一もありかなとは感じています。そうすれば停車位置変動することはなくなります。
(でも空気輸送度が上がりますが)
通勤通学時間は学生等の利用も結構あるみたいなので6連説もあると個人的には感じています。
まあ最終的にはJR九州の考え次第なのでそこらへんどうなるのか今後も要チェックです。
長文失礼致しました。(再)