豊田車両センターの中央快速線・青梅線・五日市線用E233系0番台の予備編成が不足している影響か、定期列車の運休や所定外編成の代走が頻繁に見られるようになっています。
定期運用を持つE233系は12両貫通編成(T編成)・12両分割編成(H編成)・6両編成(青600編成)・4両編成2種(青400編成・P編成)ですが、青400編成以外の編成は予備1編成、青400編成に至っては予備編成が存在しません。
青梅線内の終日10両編成運用はグリーン車を組み込んでいない・グリーン車組み込み対応改造対象から外れた10両貫通編成を使用して代走していますが、12両編成しか運行できない中央快速線内の運用は、先述の通り平日朝ラッシュ時の1運用分(主に21T)を運休とする措置がとられてしまっており、旅客への影響が生じています。
E233系は機器更新による長期入場が数年間続くことが見込まれ、予備編成が不足する状況は今後も現実的であると考えられますが、この状況への対策が講じられることはあるのでしょうか?

E233系トタT40編成が青梅線運用に充当
本日、E233系0番台トタT40編成が青梅線内完結の10両編成運用に充当されていることが確認されました。同編成は中央快速線グリーン車組込準備改造が実施されたものの2025年3月ダイヤ改正のグリーン車サービス開始時点で組込対象外となり、改正以

中央快速線で車両故障による運休が発生
複数の目撃によると、本日、中央快速線の21T運行が車両故障のため運休となりました。トタT10編成が長野入場中、H50編成が東京入場中で、目撃のないT31編成が故障したものと推測されます。トタT40編成(G車準備済み)は豊田車両センター留置中

トタT71編成が青梅線運用に充当
本日、E233系0番台のグリーン車非組み込みT編成であるトタT71編成が青梅線内運用の11運行に充当されています。同編成の営業運転入りはダイヤ改正前以来になります。なお、4月には同じくグリーン車非組み込みT編成であるトタT40編成も青梅線内

中央快速線で再び運休発生
複数の目撃によると、7月2日、中央快速線21T運行が運休となりました。グリーン車組み込み以降、2回目の確認となります。6月25日発でトタH52編成、6月30日発で青461編成、青663、T40編成、7月1日発でT8編成が豊田から東京・長野・
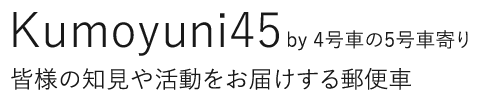



コメント
機器更新による長期離脱で車両が不足した場合、運休も折り込み済みということなのでしょう。
過去の車体保全入場の際は、青659編成を現H59編成として用途変更した実績がありますが、そもそもグリーン車が普通車の数よりも1ユニット分少ないわけで組み込み対応済みのT40編成を中央快速線の運用に入れようにも入れられない状況ですので、1ユニット分のグリーン車を追加増備して予備車確保、利用もある程度は戻っている筈ですので機器更新完了後は56運用58本体制に戻す(運行機会微増によるグリーン車による増収も狙う)のが一番丸く治るような気がします。
グリーン車1ユニットを新製してしまえば簡単でしょうけど、機器更新終わりました、はい廃車、とは行かないです。
廃車せずに使う見込みが立つのであれば細かい不便を生じさせずに現に存在させているはずですが、
ましてや計画として出た製造数から2両1ユニット削減した経緯すらあります。
度々ご意見をお書きのようですが、同感された方がどのような共通認識をお持ちか存じませんが、その理由の説明が足りてない現状では成立しないと受け取っています。
『余れば今の運行区間で多く列車を走らせれば良いのでは?』といった対応はたとえ素人が見たところでされておりません。されているのであればE233系1000番台やE235系0番台などに余剰が出ている現状は見られないことになりますが、現実の需給判断のもとの対応に反しています。
その後の用途について議論された鉄道ピックアップがあれば、そのリンクを改めて示して頂ければ幸いです。
ID:M4MTA4NTUさんはただ余っているから再増発しろとは仰られておらず、
「利用もある程度は戻っている」
「運行機会微増によるグリーン車による増収も狙う」
という理由を明示してグリーン車1ユニット新製→再増発、と考察されていませんか?
ID:MzNzA5NzAさんも運営とも他のコメント参加者とも違う立場を意識したようなコメンテーターとして今まで多数コメントされているように見えますが、今回は藁人形論法のように思ってしまいました。
>廃車せずに使う見込みが立つのであれば細かい不便を生じさせずに現に存在させているはずですが、
>ましてや計画として出た製造数から2両1ユニット削減した経緯すらあります。
元々明らかに57本に削減するような動きだったのにも関わらず58本目の組み込み対応改造が行われた辺り、削減の後に再び戻すような判断が生じた可能性があり、従って新製するグリーン車もキャンセルの後に再発注の動きがあったのかもしれません。
であればキャンセル前と全く同じスケジュールで製造することは難しいですから、今のようにグリーン車と組み込み対応編成の数に齟齬が生じてしまうことはあり得ると思います。
組み込み対応改造の方は早く着手できた理由は気になるところですが、過去の総合車両センター公開を見ていても、改造や更新用機器を実際に使用する前からストックしている状況は十分に考えられますから、こちらは既に改造用の部品の調達が済んでいた(仮に数が削減されたままであれば未使用予備品となる見込みだった)、辺りでしょうか。
> 削減の後に再び戻すような判断が生じた可能性があり
> キャンセル前と全く同じスケジュールで製造することは難しい
ご指摘を基準に、ではいつ頃このコメントの件が明らかになるか整理すると、
グリーン車製造を1ユニットキャンセルしたのがメディアから明らかになったのが2023年11月頃で、
T40編成がG車組み込み対応改造で入場した
(ご指摘の中で、グリーン車組み込み実施編成数を当初計画に戻した可能性があると判明した)のが2024年5月となっています。
機器更新そのものは1か月半程度を要しているようですから、
2025年6月30日に入場したT40編成が機器更新完了済(8月下旬ごろ?)となってから
操車対象になるかどうかはそれ以降に判明することになりますね。
リピートオーダーには通常1年半〜3年程度掛かっているようなので、結論が判明する
(グリーン車追加新製の有無が明らかになる)のは概ね今年の秋以降でしょうか。
※明らかになる というのはここでは内部情報や車両出場の情報が出回ったとかそういうものではなくて、
目撃情報(撮影不可のため)などで客観的に事実を把握できた時期。
ダイヤ改正で運用数をさらに削減するか?
昨年(2024年)ですが10月にダイヤ調整が行われたことがありましたが、これは主に実施されるなら3月中旬に行われますので、
判明時期が最も遅いことになります。
需要に関してはコロナ禍前の約9割程度にまでは回復しているとのことでしたが、
コロナ禍前より増加した・ほぼ同水準となったとの情報は発見できませんでした。
他の方も指摘していますが、グリーン車連結分の輸送力増加が運用本数減の比ではないので、
本数まで増やす(復元する)のかと言えばやはり疑問が残りますがどうなるでしょうね。
細かく計算はできていないですが、グリーン車増結は言い換えれば一般車両の全てで増車による輸送力増強を行ったわけで、実は特急廃止や一般車1運用運休による輸送力減少を補えてしまうのかもしれません。
こういう背景があるからかは分かりませんが、平気で運休にする会社が今の状況をあまり問題視しているようには思えないのです。
あまりにも運休が多い場合は、来年の改正で減便されそうです。
1往復減らしたところでグリーン車増結分の方が上でしょうし、それほど影響ないかもしれません。
> E233系は機器更新による長期入場が数年間続くことが見込まれ、予備編成が不足する状況は今後も現実的であると考えられますが、この状況への対策が講じられることはあるのでしょうか?
運用数などのデータに詳しいコメントは他の方にお任せしますが、卵が先か鶏が先かの問題で、車両原因での運休要因を削減するための機器更新ならば致し方が無いようにも思われます。
原因がいずれにしてもダイヤ乱れや運休が頻繁に発生するものだと利用者側が認知している状況にあります。
2028年末頃と目される主要駅でのホームドア設置が完備されれば乗降客原因でのダイヤ乱れが緩和されるとは思いますが、車両原因によるものはこれは関係のないことで、
2年前のデータで最混雑率が158%とも出ていますし、敢えてがんじがらめで何が何でも列車を走らせなければならない認識は既にないでしょう。
もしかしたら、運休が単独の車両原因として詳らかになって批判を浴びないために、『今のうちに機器更新をどんどん実施してしまえ!』みたいなところがあるかも知れませんよ。だとすれば個別に車両故障が発生しようが意に介さず機器更新のための編成を送り込んでいくことでしょう。むしろ擦れた感覚で、JR側にも潔い割り切りが見て取れます。
グリーン車組み込み前は、検査や故障離脱に備えた予備も込みで比較的上手く回していた気がしますが、何故この体たらくになってしまったのでしょうか。
元々青編成とT/H編成は運用が別ですのでグリーン車組み込みのせいではないでしょう。
そもそも機器更新を実施するとなると定期検査と被せてもなお長期離脱は免れませんが、「青編成から着手するのか」「T/H編成から着手するのか」「新製からまもないグリーン車は除外するのか」といった、この辺さえもあまり深く考えておらず、行き当たりばったりとしか思えない状況です。何でもかんでも外野の声は聞く必要は無いですが、せめて「身内」たる現場の声ぐらい拾い上げるべきだと思います。
>元々青編成とT/H編成は運用が別ですので
その頃は編成構成が同一で、運用こそ分かれていても実際には頻繁にT/H運用に青編成が入り、同様に青運用にH編成が入っていましたから。
実質的に予備車が共通でしたから問題なんてまず出ようがありませんでした。ワンマン化の実施前でしたからH編成でも青編成でも4両運用に入れましたし。
そもそも(計画?)運休って駅員はともかく工員や乗務員といった現業はそんなに困らないような・・・
まぁ、極端なまでに突き詰めた保有資産の合理化の負の側面ではありますよね。
最近だと東武東上線でも似たようなことが起こってましたっけ。
東武は元々予備多めですが、それを良いことに長期休車させたりする傾向にあるのでまた別の話ですね。
>東武は元々予備多め
それは少し前までの話で、その後休車編成(9101F・11004F等)をほぼ一通り廃車にしましたから、今はまったく予備車無いですよ。
東上線のほうでは中央快速と予備車事情はほとんど変わらなくなってます。
現場ではこうなることが分かった(こうすることを決めた)上での機器更新・入場スケジュールでしょう。代走、代走、ダメなら運休…と複数の対応を予め決めておけば現場はバタバタしません。新造・転入を伴う対策はなされずこのまま機器更新完了まで乗り切ると思われます。
そうなると、以前にここで出されたお題「JR東日本の線区に今後「希少車種」が中長期的に発生することはあるのか?」は、発生しないということになるでしょうね。
ぶっちゃけT40を活用すれば運休は回避出来そうだと思うのですが、現実はそう単純な話ではないのでしょうか?
T40について見落としがちなのが、実はグリーン車組み込みに対応している点です。
他編成が機器更新や急な故障も含めて離脱しても、グリーン車をもらってT40を12両化すれば離脱編成の代わりになりそうだとは思いますが。
実際T40の10両ステッカーを剥がしたそうで、グリーン車を組み込むつもりだったのかなと思いました。
「グリーン車をもらってT40を12両化すれば離脱編成の代わりになりそうだとは思いますが。」
12両でそのまま入場させ、何故かこれをやろうとしないからこのような議論になっているんだと思いますよ。この方法ならT40の組み込み設備も無駄にはならずそもそも以前から趣味者の間でもこの方法で機器更新を乗り切るのではとは散々言われてきていましたが、組み替えは極力避けたいのでしょうか。
列車を運休させてでも現場の負担を減らしたいのかと思いました。
冷静に考えると機器更新で編成が離脱するたびに毎回毎回編成替えをするってかなり大変なのかもしれません。
とは言っても(過去の話になりますが)、山手線E231系の6扉車→4扉車を置き換えのように全編成を組み替えた例があります。
今回のE233系も同じように組み替えを行えば良いと思いますが、やらない(出来ない)理由が何かしらあると。例えば現場の人手不足とかでしょうか?
T40のグリーン車組み込み準備は今のまま活用されないなら本当に勿体ないですね。
まず大前提として、計画では当初よりT/H編成の予備は計2本となる予定でしたので、機器更新期間中に生じる突発的な運休というのは当初から織り込み済みであり、現状では想定した通りの取り扱い以上の話ではないものと思われます。
ただ、外野から見た時に計画外の予備であり改造理由もはっきりしていないT40編成というイレギュラーな存在が話をややこしくしている感じですね。
定期列車の恒常的な運休は国交省に説明が付かないといけませんから、「編成が不足すれば運休にすればいいや」と言う考えなら、ダイヤ改正時に減便していたと思います。現実に合わせて組み換えをしない理由を考えると、酷暑の熱中症対策で検修作業に計画外の休憩を挟んでいて、臨時検査班や大修班をそのフォローで使ってしまっている、組み換え作業の要員が捻出出来ないのではないかと思われます。
そうすると、秋口からは運休回避で組み換えて入場させるように予想しますが、いかがでしょうか。
今日そのトタT40がトタT8が組んでいたサロ56番を組み込んで長野を出場したらしいので、わざわざ手狭な豊田に人員手配をするよりは、工場がある長野までトタT40を回送させたのかなと。回送させる手間こそは要するものの、人員的にも編成組み替え作業のスペース的にも都合がよかったのかなと。実際半年で約55編成分にサロを組み込む時も豊田ではスペース的にも時間的にも手一杯だったので、幕張や国府津でも組み替え作業を行なったといえば話が合う気もするので。
減便で対処でしょう。